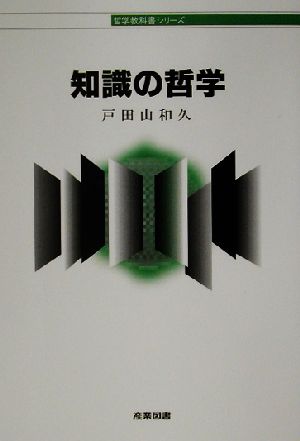知識の哲学 の商品レビュー
本書で考える問いはどんなものか。以下のような場面を想像してみよう、という筆者の提案からはじまる。 * あなたと弟が学校から帰ってきたら、テーブルの上にきれいな包装紙に包まれた箱が置いてあった。二人は同時に「シュークリームだよ、きっと!」と叫ぶ。… 箱を開けてみると本当にシューク...
本書で考える問いはどんなものか。以下のような場面を想像してみよう、という筆者の提案からはじまる。 * あなたと弟が学校から帰ってきたら、テーブルの上にきれいな包装紙に包まれた箱が置いてあった。二人は同時に「シュークリームだよ、きっと!」と叫ぶ。… 箱を開けてみると本当にシュークリームが入っていた。なんでシュークリームだと思ったのかと尋ねる弟に、あなたは「なんかそんな気がしただけ」と答える。一方弟の答えは、「今朝、おかあさんがおやつにシュークリームを買っておくから帰ってきたらおねーちゃんと一緒に食べなさいって言ってたんだもん。」。「なーんだ。あんた知ってたんじゃない!」 二人ともシュークリームが入っていると強く思っていて、二人の思っていたことは正しかった。でも弟はシュークリームが入っていたことを知っていたと言えるのに対し、あなたの場合はそうは言えないみたいだ。この違いは一体どこにあるのだろう? * この冒頭のエピソード大好き。筆者が言う「哲学の問いは日常の中に転がってる」というのをよく表してるし、「うーん、何が違うか。理由があるか、ないか、かな?」と読者を引き込ませるし、読み進めるうちに「ハテ。一体この本で何を考えていたんだっけ?」となった時に「ああそうだ、シュークリーム」と問いに立ち戻れる。
Posted by
著者も前書きで述べている通り、自然主義の立場に偏った認識論入門書。入門書なのでいずれの項目もあまり詳しくは書かれていないが、伝統的な認識論と新しい認識論のだいたいの流れはつかめる良書。ただ、誤った記述がまれに見受けられるのでマイナス1点。
Posted by
知識の古典的定義に始まり、新しい認識論が生み出されるまでや、今日的意義が次第に明らかになってくる。 哲学が現代でも様々な理論や解釈を生み出し、現代社会に応じたものになっていることを感じさせてくれる。
Posted by
本書は哲学の二大カテゴリである形而上学と認識論のうち後者を解説しています。「教科書」とあるため敬遠されるかもしれませんが、そう銘打つだけあって、知識ゼロの人でも理解が容易の内容となっています。私は日ごろ哲学に触れない理系の学生なので、頭の体操としてちょうどいい本でした。哲学に興味...
本書は哲学の二大カテゴリである形而上学と認識論のうち後者を解説しています。「教科書」とあるため敬遠されるかもしれませんが、そう銘打つだけあって、知識ゼロの人でも理解が容易の内容となっています。私は日ごろ哲学に触れない理系の学生なので、頭の体操としてちょうどいい本でした。哲学に興味があるけど、どこから手をつければいいかわからない人にお勧めの本です。 (北九大 情報工学専攻 T.K.さん)
Posted by
人はいかにして世界を知ることができるかという、いわゆる認識論のテキスト。総花的に理論を説明するのではなくて、そもそも知るとは何かを「正当化された真なる信念(Justified True Belief)」から一つ一つ検討していきます。読み手にも頭を使って考えさせるので、なかなか手応...
人はいかにして世界を知ることができるかという、いわゆる認識論のテキスト。総花的に理論を説明するのではなくて、そもそも知るとは何かを「正当化された真なる信念(Justified True Belief)」から一つ一つ検討していきます。読み手にも頭を使って考えさせるので、なかなか手応えがあっておもしろい。ただ、半分くらいでもう置いてけぼりになったので、そのうちまた読みなおそう。
Posted by
*購入 親しみを感じさせる文体ですが非常に深い内容です。教科書としてはぴったりなのでしょう。 例も豊富で、文体も比較的やわらかめ、言葉を尽くして説明してくれている感はあるのですが、どうしても内容的にとっつきにくい… なんどか読み返して慣れようと思います。
Posted by
親しみやすい口調で書かれていますが、本格的な認識論の教科書です。単に「そう思う」ことと「知っている」ことの違いからはじめ、「絶対確実な知識」からほかの知識を保証する基礎づけ主義の問題点を論じ、基礎づけ主義がどうして歴史上現れたのかという問題、つまり、懐疑論への反駁を述べます。余談...
親しみやすい口調で書かれていますが、本格的な認識論の教科書です。単に「そう思う」ことと「知っている」ことの違いからはじめ、「絶対確実な知識」からほかの知識を保証する基礎づけ主義の問題点を論じ、基礎づけ主義がどうして歴史上現れたのかという問題、つまり、懐疑論への反駁を述べます。余談ですが、この部分は中国哲学における仏教との対立を思い出しました。儒教や道教も仏教の空や唯識の理論への反駁を鍛えることで発展したといえるからです。著者は懐疑論を「懐疑の水増し装置」としてとらえ、デカルトの懐疑論の反駁を論じ、それが不十分であること、シジックによる懐疑論への反駁、懐疑論が懐疑を水増ししていくプロセスに焦点をしぼった反駁、を論じている。クワインについては、認識論の自然化というキーワードを軸に論じ、認識論が「第一哲学」ではなく、心理学や脳科学の一部であることを論じます。さらにクワインを反駁したスティッチの議論を紹介し、認識論には道具的意味があるが、道具として奉仕するその目的は「真理」のためとは限らないことについて詳細に論じます。著者の主張としては、認識論には、自然化をしたうえで、「さよなら」をし、さらに、個人主義からぬけだし社会化しなければならないといいます。日常的にも、科学の先端においても「集合知」を用いないことには、何も知らないことになってしまうからです。そして、最後には、新しい認識論の構造を論じ、自然科学・科学史・情報学(自然そのものが情報をもつ)・コンピュータ(人間という生物に認識不可能なものも認識可能にできる)などを取り込んで、発展すべきだといいます。また、信念や真理といった個人の心に宿るものはいらなくなるかもしれないといっています。なかなか複雑なので、何度か読む必要があり、また、教科書なので課題が設定してありますが、なかなか難しい問題ばかりです。哲学とは永遠の問題をずっと考えているような、ほかの学問と切り離された営みではなく、それぞれの時代に要求されるバラバラな試みだからこそ面白い、という意見には賛成です。哲学では自由に問題を問えることが面白いのではないかと思います。内容は、ある理論の説明がなされたあとに、それに対する反論や限定などがつづいて、よみがいのあるものです。決して学説史ではなく、自分でものを考える訓練ができる本です。「マトリックス」にはまって、「心なんて、脳のなかの化学反応にすぎない」と知ったかぶりしている人、古典的認識論にはまっている人はぜひ読んでみるといいと思います。例が「ちびまる子ちゃん」や「めぞん一刻」や「ゴレンジャー」などで作られているのは、著者のユーモアを感じます。
Posted by
「知っている」とはどういうことなのでしょうか。400年以上に渡る人類の戦いの軌跡がこの一冊に。コギト・エルゴ・スム登場の文脈を知らない人は読むように。戸田山先生の名著です。
Posted by
- 1