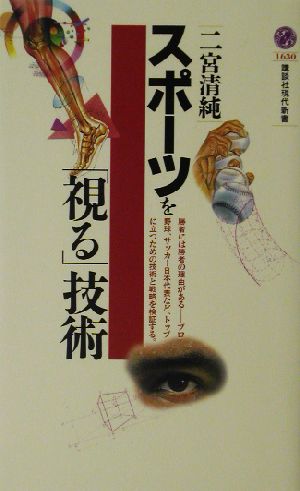スポーツを「視る」技術 の商品レビュー
『つながる読書術』から。そうか。勝手に思い描いた内容としては、このスポーツはこんな風に見ればもっと楽しめますよっていう、その指南書かと思ってました。でも実際は、作者が記者としての”視”点を披瀝することにより、いかにしてスポーツ記事が書き上げられるかについての解説書。思っていたのと...
『つながる読書術』から。そうか。勝手に思い描いた内容としては、このスポーツはこんな風に見ればもっと楽しめますよっていう、その指南書かと思ってました。でも実際は、作者が記者としての”視”点を披瀝することにより、いかにしてスポーツ記事が書き上げられるかについての解説書。思っていたのと違うっていうのと、新書の形態をとって入るけど、実は雑誌みたいな内容っていうのがあって、あまり好きになれない作品でした。
Posted by
著名なスポーツ選手のインタビュー集。 視る技術というよりも、著者の視点を見て欲しいという書きっぷり。帯に若干騙された感。 ただこういう視点でスポーツを見られると、今よりもっと楽しめると思う。
Posted by
スポーツをするのも視るのにも、殆ど興味のない僕のような人間でも、思わず「スポーツを視てみたい!」という気持ちになる本だ。プロスポーツの巧拙は、運動神経や天性の才能の有無で片づけ、思考停止に陥りがちだけど、スポーツにおいて、戦略、戦術、技術を磨くのに、たゆまぬ努力と深い分析能力が不...
スポーツをするのも視るのにも、殆ど興味のない僕のような人間でも、思わず「スポーツを視てみたい!」という気持ちになる本だ。プロスポーツの巧拙は、運動神経や天性の才能の有無で片づけ、思考停止に陥りがちだけど、スポーツにおいて、戦略、戦術、技術を磨くのに、たゆまぬ努力と深い分析能力が不可欠であることがわかる。
Posted by
[ 内容 ] 勝者には勝者の理由がある―プロ野球、サッカー日本代表など、トップに立つための技術と戦略を検証する。 [ 目次 ] 第1章 プロ野球を語る視点(指揮官とは何か―西武・伊原春樹監督の発想法;メジャーリーグの流儀;孤高の天才打者―前田智徳という精神性) 第2章 サッカー...
[ 内容 ] 勝者には勝者の理由がある―プロ野球、サッカー日本代表など、トップに立つための技術と戦略を検証する。 [ 目次 ] 第1章 プロ野球を語る視点(指揮官とは何か―西武・伊原春樹監督の発想法;メジャーリーグの流儀;孤高の天才打者―前田智徳という精神性) 第2章 サッカーを語る視点(トルシエ・ジャパンの総決算―日本代表全四戦の軌跡;これが世界の戦いだ―ゲームの語り方;川淵三郎インタビュー―ジーコへの期待、改革への志 ほか) 第3章 歴史を変える者たちへの視点(高橋尚子―シドニー五輪金メダルを決めた「勝負の分かれ目」;原田雅彦―長野五輪を制した波乱万丈のジャンプ;徳山昌守vs.名護明彦―「距離」を破れなかった挑戦者 ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
面白かったのは序文だけ。観戦のプロだけが持っている極意の片鱗を見せてもらえるかな、と勝手に期待して読んだんですがね……。ただのインタビュー集でした。
Posted by
野茂やジーコや猪木のインタビューも載っていてフツーにスポーツコラム集として楽しめます。 そんな中で一番僕の心を捉えたのは、最後の高橋健次さん(故人、アイスホッケーの日光アイスバックスとちぎ元社長)のインタビューでした。自分の「いのち」を削りながらでも、アイスバックスを市民クラブ...
野茂やジーコや猪木のインタビューも載っていてフツーにスポーツコラム集として楽しめます。 そんな中で一番僕の心を捉えたのは、最後の高橋健次さん(故人、アイスホッケーの日光アイスバックスとちぎ元社長)のインタビューでした。自分の「いのち」を削りながらでも、アイスバックスを市民クラブとして根付かせようとした氏の努力には敬服します。「いのち」の使い方について、ちょっと考えさせられました。
Posted by
- 1