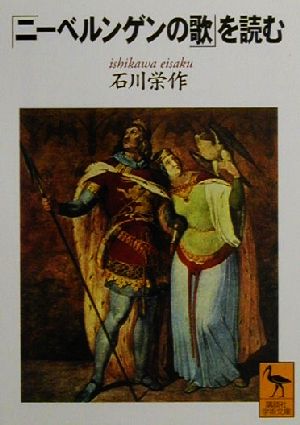『ニーベルンゲンの歌』を読む の商品レビュー
中世ドイツ最大の叙述…
中世ドイツ最大の叙述詩の『ニーベルンゲンの歌』の解説本です。本書を読まれた方は是非原典を。岩波文庫から出てます。
文庫OFF
中世ドイツ最大の叙述…
中世ドイツ最大の叙述詩の『ニーベルンゲンの歌』の解説本です。本書を読まれた方は是非原典を。岩波文庫から出てますよ。
文庫OFF
ドイツの中世英雄叙事詩を、前編、後編に分け、丹念に読み解きます。 成立やこれ以降のジークフリート伝承のながれについても解説してくれます。 さまざま要素が対立して構成されているのが、わかりやすく書かれています。
Posted by
『ニーベルンゲンの指輪』というと、まずワーグナーの指輪四部作で有名だけど、私が最初に知ったのは池田理代子氏の漫画『オルフェウスの窓』だったりする。作中の前半はドイツの音楽学校(男子のみ)を舞台にしていて、謝肉祭のお祭りに学生達が「ニーベルング」の劇を上演するというストーリーがあっ...
『ニーベルンゲンの指輪』というと、まずワーグナーの指輪四部作で有名だけど、私が最初に知ったのは池田理代子氏の漫画『オルフェウスの窓』だったりする。作中の前半はドイツの音楽学校(男子のみ)を舞台にしていて、謝肉祭のお祭りに学生達が「ニーベルング」の劇を上演するというストーリーがあったのだ。主人公のユリウス君が、実は遺産相続のために男として育てられた女性だったり、それが女装(?)させられてクリームヒルト役をさせられたり、あんまり美人なので周囲が騒然としたり……と、こう書くと昨今のBLっぽくて苦笑いしちゃうんだけど、当時は凄くドキドキしました。それで、『ニーベルンゲンリング』については物凄い刷り込みが行われちゃったんだろうと想像。 その、ニーベルンゲンの真面目な伝承から歴史的検証、その他を学術的に研究した本なので、私自身の「萌え」とは明らかにかけ離れた内容ですが、それはそれとして非常に興味深いです。ドイツ英雄譚の「ジークフリート」とか、ブリュンヒルデがどういう存在かとか、細かい筋立てに他バージョンがあるという話とか。
Posted by
今回改めて読み直してみて、一番 KiKi の注意をひいたこと。 それは「第4章 悲劇の二重構造」の中にある以下の記述でした。 ジーフリトの死にはニーベルンゲン財宝の霊力が働いていたことが明らかである。 ジーフリトは今やニーベルンゲン族と呼ばれていることにも注目する必要がある...
今回改めて読み直してみて、一番 KiKi の注意をひいたこと。 それは「第4章 悲劇の二重構造」の中にある以下の記述でした。 ジーフリトの死にはニーベルンゲン財宝の霊力が働いていたことが明らかである。 ジーフリトは今やニーベルンゲン族と呼ばれていることにも注目する必要がある。 ニーベルンゲン (Nibelungen) とは「霧の国の人々」、すなわち、「冥界に行くべき人々」を意味し、ニーベルンゲンの宝を持つ者は滅びなければならない。 ジーフリトはニーベルンゲンの宝の所有者となり、ニーベルンゲンの国の主人となったがために、滅びなければならない運命にあるのである。 ここには古代ゲルマンのニーベルンゲン伝説に由来する不思議な力が作用しており、前編の主人公ともいうべきジーフリトは最初から死すべき運命にある古代ゲルマンの英雄である。 (以下略) このように前編では侏儒族からニーベルンゲンの財宝を奪い取ったジーフリトがニーベルンゲン族と呼ばれていたのに対して、後編においてはフン族の国へ出かけるブルゴント族がニーベルンゲン族と呼ばれていることは注目すべきである。 今や滅びていくのは、ジーフリトから財宝を奪い取ったブルゴント族である。 前編と同じように後編においてもここでは素材に由来する財宝の呪いが支配しており、ブルゴント族は、ニーベルンゲンの財宝をクリエムヒルトから無理やり奪い取ったがためにジーフリトと同様、所有するや否や、滅びていかなければならないのである。 (以下略) (本文 p.215-216 より転載) 以前、KiKi は「ゆびわの僕(裏ブログ)_Lothlórien開設時にこちらに統合」で「ニーベルングの指環が象徴するもの」というシリーズもののエントリーを書いているのですが、その頃にはこの本を一読していたにも関わらず、ここに書かれていた内容に関してはすっかり頭から抜け落ちていました ^^;。 (全文はブログにて)
Posted by
ニーベルンゲン伝説の系譜を追うことを生涯課題と宣言した著者,石川栄作氏。過去から現在そして未来まで。なによりコミック化まで視野に入れていることにびっくり。脱帽です。
Posted by
- 1