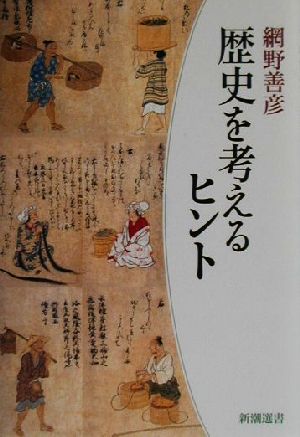歴史を考えるヒント の商品レビュー
「百姓は100の仕事を指す言葉だから、農業だけじゃなく実にいろんなお仕事をしてた人々だったと考えられているんだよ!」かつて勤務していた塾で社会を教えていた時必ずしたこの話は、網野さんの書籍に大いに影響を受けています。 自虐史観だと批判されることがあるというが、被差別民や百姓として...
「百姓は100の仕事を指す言葉だから、農業だけじゃなく実にいろんなお仕事をしてた人々だったと考えられているんだよ!」かつて勤務していた塾で社会を教えていた時必ずしたこの話は、網野さんの書籍に大いに影響を受けています。 自虐史観だと批判されることがあるというが、被差別民や百姓として生きたご先祖様に対してリスペクトを感じるし、本書にも書かれているように日本語に対する愛着も非常に強い。 日本史を考える1つの見方として大変興味深く拝読させていただいた。
Posted by
☆2001年発行 2004年筆者死去 国名が決まった時期→浄御原令(きよみはらりょう) 689年天武天皇 土産(みやげ・土の字→その国の、その土地のという意味あり) 神奈川の大学で講義 同和問題 関東出身の学生は童話と勘違い 地域による実態の違い ケガレ・清め 商業用語 ...
☆2001年発行 2004年筆者死去 国名が決まった時期→浄御原令(きよみはらりょう) 689年天武天皇 土産(みやげ・土の字→その国の、その土地のという意味あり) 神奈川の大学で講義 同和問題 関東出身の学生は童話と勘違い 地域による実態の違い ケガレ・清め 商業用語 小切手、手形、為替…→中世から古代にまで遡る 中央自動車道談合坂 相談事が行われた神聖な場所の意・神の前で共食しながら神に互いの約束を誓う・商業取引において当然のこと
Posted by
学校で習った日本史からより深く学びたい人におすすめしたい一冊。 日常の言葉に隠された歴史、日本の国名や地名の由来、関東と関西の相違点など、身近な視点から歴史を解説してくれるので、誰でも読みやすい内容になっている。 この本で一番の読みどころは百姓の多様性について書いてあるところ...
学校で習った日本史からより深く学びたい人におすすめしたい一冊。 日常の言葉に隠された歴史、日本の国名や地名の由来、関東と関西の相違点など、身近な視点から歴史を解説してくれるので、誰でも読みやすい内容になっている。 この本で一番の読みどころは百姓の多様性について書いてあるところだろう。百姓=農民というのは単純化のしすぎで、百姓には、漁民、商人、林業や塩業の従事者などあらゆる人々がいたということである。 学校で習うようなありきたりな歴史観が隠しがちな事象に光を当ててくれるので、読めば確かに「歴史を考えるヒント」になるだろう。
Posted by
網野史観で有名な網野氏の歴史と 言葉を考える内容の本。 有名な百姓という言葉や、日本・関東・関西・ 切手・落とす・自由・・・などの言葉の解釈が 現代と古代・近世との意味の違いがあること。 その違いを大事にして歴史をみる必要があること が語られている。
Posted by
「百姓」のイメージの話は前々から聞いてはいたけど、 改めて読ませていただくと勉強になる。 歴史を叙述するのに、言葉の意味を考えることが大切という文脈はとても頷ける。 歴史だけじゃないよね。言葉は伝わってこそのものです。
Posted by
(2001.02.14読了)(波・連載) (「MARC」データベースより)amazon 普段何気なく使っている言葉に意外なほど長い歴史がこめられ、深い意味のある例は少なくない。関東、関西、手形、切手、自由、自然などの言葉を通して、「多様な日本社会」の歴史と文化をわかりやすく語る。...
(2001.02.14読了)(波・連載) (「MARC」データベースより)amazon 普段何気なく使っている言葉に意外なほど長い歴史がこめられ、深い意味のある例は少なくない。関東、関西、手形、切手、自由、自然などの言葉を通して、「多様な日本社会」の歴史と文化をわかりやすく語る。『波』連載を編集。
Posted by
土産の土は、その土地のという意味 切手の手は、交換の意味が 自然には、じねんと読み、万が一という意味もあったなど、言葉の意味から日本の当時の状景を語った興味深い本 2012.12.9読了
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「日本」という国名が決まったのは、浄御原令(きよみはらりょう;天武天皇が編纂を開始し、死後その皇后の持統が施行)という法令が施行された689年とされている。大宝律令が制定された701年の翌年、中国大陸に到着した遣唐使の粟田真人が当時の周の皇帝・則天武后(女帝で、国号を唐から周に変えた)に対して、「日本」の使いであると述べたのが最初と言われている。 「倭」→「日本」
Posted by
孤立した島国、日本。って刷り込まれてきたが、地図を上下逆さまにした「環日本海諸国図」をみると、日本海は湖みたいなもんで列島はまるでアジア大陸南北の架け橋のよう。大陸からの人とモノの流入はそりゃ凄かったんだろうし、東西でルーツも異なる…と。 差別や金融用語の由来など、いわゆる「通...
孤立した島国、日本。って刷り込まれてきたが、地図を上下逆さまにした「環日本海諸国図」をみると、日本海は湖みたいなもんで列島はまるでアジア大陸南北の架け橋のよう。大陸からの人とモノの流入はそりゃ凄かったんだろうし、東西でルーツも異なる…と。 差別や金融用語の由来など、いわゆる「通史」感のある歴史家が詳細に解説。
Posted by
「この書物が「歴史」と「ことば」に対する関心を多少なりとも刺戟し、世の中に拡がる小さなきっかけになれば、幸いと考えています。」 わたしも大学に入ってから思い知らされたことですが、わたしたちが高校まで、常識だと教えられてきた日本史と、歴史学の先端をゆく歴史学者の日本史は、往々に...
「この書物が「歴史」と「ことば」に対する関心を多少なりとも刺戟し、世の中に拡がる小さなきっかけになれば、幸いと考えています。」 わたしも大学に入ってから思い知らされたことですが、わたしたちが高校まで、常識だと教えられてきた日本史と、歴史学の先端をゆく歴史学者の日本史は、往々にして一致しません。 例えば鎌倉幕府の成立に関する、「いいくにつくろう鎌倉幕府」も、既に否定的な見方が主流です。 そういった、わたしたちが信じ込んでいる日本史の姿を今一度見直し、分かり易く解説しているのが、この本です。 「関東」や「関西」等、地名の歴史をはじめとして、「百姓」などの身分にまつわる言葉、「切手」や「手形」といった経済用語の歴史をひもとき、その言葉の背景にある日本の姿を推測しています。 わたしは特に、「小切手」「手形」「為替」といった用語が中世から存在し、そのルーツは古代にさかのぼるのではないか、という話が面白かったです。 現代のような経済の仕組みの原型が、それほどまでに昔に既に成立しており、江戸時代には農本主義どころか重商主義の傾向さえあったというのには驚きです。 また、「文明開化以前の日本は農民ばかりで、経済は全然発展していなかった」という今のわたしたちのイメージを植え付けたのが、文明開化後、欧米列強の影響を受け、それらに追いつこうと必至こいている政府であった、という話も興味深かったです。 この本の中には憶測でものを語っている部分が多く、すべてを信じるには根拠とするのものが偏っていたり、曖昧なものも多いですが、「歴史を考えるヒント」という目的では、歴史を考えるきっかけとしての役割を充分果たし得るのではないかと思います。
Posted by
- 1
- 2