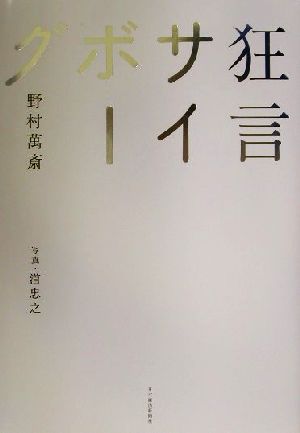狂言サイボーグ の商品レビュー
おすすめです
萬斎さんが、まだ武司だったころも綴られていて なおかつ、解説があります 能の世界、ここがポイントだ!みたいな 各項目ごとの写真はとても美しいです 写真も内容もたっぷりですから(生き生きと萬斎さんが語ってくれています) 納得の一冊かと
しずく
野村萬斎って何を考えて生きているのだろう、という純粋な疑問から手に取ってみた。 とても現実的で論理的に一つ一つ詰めていく、それでいて心で感じることを忘れていない面白い人だと思った。ユーモアも独特でちょっと変わった人だな、でもそこがいいなあってさらに興味が湧いた。
Posted by
著者は軽いエッセイのつもりで書いたのかもしれない。 読者にとっては現代において伝統芸能に取り組む人の格闘の記録であり、哲学書の類を読むような緊張を感じながら読みました。
Posted by
野村萬斎さんが書いた狂言の本。 若い時から連載してたエッセイをまとめたもので、失礼ながらだんだん文章がうまくなっていって、わかりやすくなっているなあと思った。 狂言をテーマ別にわかりやすく説明してあったりして、読みやすい。 萬斎さんの若い頃の写真もたくさん載ってます。
Posted by
野村萬斎さんが、自分を狂言のサイボーグとして語る本。 堅苦しくなく、思うことを素直に語った内容はとても読みやすかったです。
Posted by
野村萬斎さんが好きで、書店で見つけて思わず購入。 狂言、またご本人のこれまでについてを細かに紹介されています。 なかでも、狂言をコンピューターに、狂言の「型」をソフトに置き換えての発想がおもしろい。とても分かりやすい説明がありがたい。 おかげで「狂言」「古典演劇」にちょびっと...
野村萬斎さんが好きで、書店で見つけて思わず購入。 狂言、またご本人のこれまでについてを細かに紹介されています。 なかでも、狂言をコンピューターに、狂言の「型」をソフトに置き換えての発想がおもしろい。とても分かりやすい説明がありがたい。 おかげで「狂言」「古典演劇」にちょびっと触れることができたように思いました。(思いたい!) 同時に、自分の無知っぷりにも気付くことに。 国際化といえど、日本の伝統を知らずしてではね・・・と。(シュン・・・) 最後は詩「僕は狂言サイボーグ」で締めくくられています。 美麗な(&おもしろい)お写真も沢山掲載されています☆ Fanのみならず、古典演劇にご興味のある方にもオススメです。
Posted by
狂言師としての文章と萬斎さんの日記のような文章が 組み合わさって構成されている本。 まず「型」を習得することで「芸」を身につける様を コンピューターがプログラミングされるような視点から デジタルなものなんてありえない伝統芸能の世界を解釈し 「サイボーグ」ととった萬斎さんのセンスっ...
狂言師としての文章と萬斎さんの日記のような文章が 組み合わさって構成されている本。 まず「型」を習得することで「芸」を身につける様を コンピューターがプログラミングされるような視点から デジタルなものなんてありえない伝統芸能の世界を解釈し 「サイボーグ」ととった萬斎さんのセンスって面白いと思う。 ほとんどの文章は日経新聞に連載されたものを編集してあるのだが、 写真と巻末の「僕は狂言サイボーグ」という文章は書き下ろし。 萬斎さん好きな人は読んだらよい本だと思います。 私のイチオシは足の写真(笑)
Posted by
日本人は農耕民族だから腰は下向きに(腰を入れる)っていうのは聞いていたが、西洋・狩猟・上向きの対比で納得した気がする まんさいさんの狂言見たい 一度お能で寝ちゃったの挽回したいなwその時は一緒にやった狂言が飛んで空中回転するので、その音で起きたw これも「下に」飛ぶというのは、本...
日本人は農耕民族だから腰は下向きに(腰を入れる)っていうのは聞いていたが、西洋・狩猟・上向きの対比で納得した気がする まんさいさんの狂言見たい 一度お能で寝ちゃったの挽回したいなwその時は一緒にやった狂言が飛んで空中回転するので、その音で起きたw これも「下に」飛ぶというのは、本当に腰というか重心が下なんだなぁと思った
Posted by
プログラムされた肉体と「型」。 人間臭いイメージの伝統芸能「狂言」と、無機質、硬質な「サイボーグ」という言葉の組合せは、読む者に居心地の悪い緊張感を強いてきます。 その異物感こそ、野村萬斎氏思うツボ。してやったりの企みでもあるのでしょう。 「サイボーグ」の真意を知りたくて、ペー...
プログラムされた肉体と「型」。 人間臭いイメージの伝統芸能「狂言」と、無機質、硬質な「サイボーグ」という言葉の組合せは、読む者に居心地の悪い緊張感を強いてきます。 その異物感こそ、野村萬斎氏思うツボ。してやったりの企みでもあるのでしょう。 「サイボーグ」の真意を知りたくて、ページをめくるのももどかしく、読みはじめました。 師から弟子へ、狂言を教えるとき(多くの場合、その関係は親から子ですが)、厳しく「型」を教え込みます。 手の高さはここ。足の運びはこう。声の出し方はこう。 師がやるのを繰り返し真似させることで、型を植えつけ、全身の回路をつないで、機能させることができるようになる。 「型」を伝えることは、人間の肉体にデジタル情報をプログラミングしていくことのようだ。 そうして、「型」を覚え込まされた狂言師、「狂言サイボーグ」ができあがる。 「メソッド」と呼ばれる、まず役の人物の気持ちになりきることで、リアルな演技ができるという欧米の演技法の主流の考え方とは対極にあるのが、狂言の演技法であるようです。 この本は、狂言サイボーグとなり、表現者としての人生を歩みはじめた青年が、黒沢明に出会い、英国に留学し、蜷川幸雄に鍛えられ、異文化に遭遇し、その度に基盤である「狂言」を問い直す過程が描かれています。 そして、「狂言」って、そういうものだったのか、という「狂言入門」の知識もいろいろありました。 私がいちばん驚いたのは『狂言と「目」』と題された一文です。 狂言はもともと、面をつけて行う演技であることを前提としていて、面をかけていないときは「直面(ひためん)」と言って、自分の顔を面として扱うのだそうです。 だから、狂言には「目の演技」はない。 思わず「えーっ」と叫んでしまいました。 言われてみればそうなのでしょうが、一方で野村萬斎と言えば、強烈な目力(めぢから)を持った人だと思っていたので、狂言では目で演技しないのだということに、あらためてびっくりしました。 では、あの鋭い目遣いはなにかというと……、 大河ドラマ「花の乱」に出演したとき、共演の市川団十郎丈、萬屋錦之助さんから盗んだ。 でも、この技術も映像出演のための技術で、狂言では使えないものなのだそうです。 こんな発見もありました。 「狂言にはラブシーンがない」 『法螺侍』というシェイクスピアの『ウィンザーの陽気な女房たち』を翻案した新作狂言があるのですが、そのなかに主人公が人妻に抱擁、接吻を迫るシーンがあり、 そのような情況に対応する古典の「型」はなく、「濡れ場」の演出には皆が気まずい思いもしたりした。 これには、思わず笑ってしまいました。
Posted by
私の大好きな野村萬斎さんの著書。 中身はかたっくるしい。 ファンの人だけ楽しめればいいのかしら。 狂言に興味なかったら読む必要もないかと
Posted by
- 1
- 2