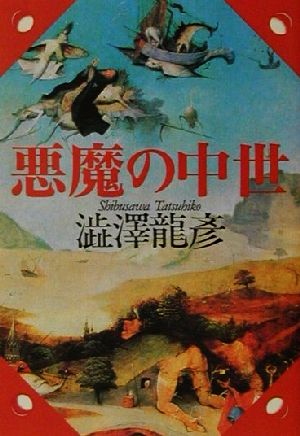悪魔の中世 の商品レビュー
「はしがき」によれば、これらの記述は著者が33歳の頃の、いわゆる「若書き」とのこと。なかなかどうして堂々たる内容、既にして恐るべき博識ぶりだ。タイトルには中世とあるが、古代から現代に至る悪魔、及びその周縁(ドラゴンだとか、地獄だとか)の、つまり反キリスト的なものの図像学史といった...
「はしがき」によれば、これらの記述は著者が33歳の頃の、いわゆる「若書き」とのこと。なかなかどうして堂々たる内容、既にして恐るべき博識ぶりだ。タイトルには中世とあるが、古代から現代に至る悪魔、及びその周縁(ドラゴンだとか、地獄だとか)の、つまり反キリスト的なものの図像学史といった内容。美が規範の上に成立しているのに対して、恐怖(これが悪魔を生む)は、無秩序と過剰のうちに成立するというのは、澁澤ならではの見事な卓見だ。虚無には際限がないのだから。ただ、肝腎の図像が暗いモノクロームで良く見えないのは残念だ。
Posted by
7/11 読了。 『神曲』の地獄と『往生要集』の地獄の類似性と日本の『九相図』に似たものがヨーロッパにもあった驚き。死の舞踏を見て、ディズニーの「スケルトン・ダンス」を見たくなった。
Posted by
前書き(という名の、刊行が遅れた言い訳/笑)によると澁澤龍彦がこの著作を物したのは30歳そこそこだったとのこと。昔の人は早熟だ。澁澤氏については人以上だったんだろうけど。そこらへんは『ユリイカ』の澁澤龍彦特集など読むと明らかになって面白いのだが、ここでは余談。 『悪魔』の『中世』...
前書き(という名の、刊行が遅れた言い訳/笑)によると澁澤龍彦がこの著作を物したのは30歳そこそこだったとのこと。昔の人は早熟だ。澁澤氏については人以上だったんだろうけど。そこらへんは『ユリイカ』の澁澤龍彦特集など読むと明らかになって面白いのだが、ここでは余談。 『悪魔』の『中世』。『悪魔』というと、現代はキリスト教以外の悪魔的なものが日常普通に跋扈していて、かえってインターナショナル…いや、この用語も古いか、グローバルな悪魔像が馴染みのものとなっても良いと思うのだが、下手にビジュアル化されることが多くてかえって人の(もっと言うと若年層の)想像力が退化していて、もっぱらキリストに対するアンチキリスト的な悪魔ばかりが超美化されて取り上げられるばかりで正直言って食傷気味。 仕事の上でも、すぐに善良=天使のような、ヨコシマな=悪魔のような、と端的もしくは安易な形容に流れてしまって非常に面白くない。 そもそも現在の、いわゆる反キリスト的な悪魔像が生み出されたのは何時で何処なのか。紀元前、というか有史以前、一神教=神=聖なると定義される以前のシャーマニズムなどまでさかのぼって、そこから一気に紀元節(ミレニアム)・西暦1000年のいわゆる世紀末の終末観に現在の悪魔像の草創を見る。ビジュアル的には旧石器時代の洞窟画から紀元前1000年ごろのアッシリア美術、十世紀ころの黙示録美術、そして十六世紀に入ってお馴染みピーテル・ブリューゲルの「叛逆天使の失墜」まで。今ある口が裂けてて黒っぽくて尻尾のある悪魔・サタン像は限られた期間にしか出現していないのだが、そこに至るまでの思想的・図象学的流れが澁澤節にのせて滔滔と語られる。いつものように洋の東西にも古今にも捕らわれない縦横無尽な引用に、読んだ当時は何がなんだかわからない学生だったが、今読み返すと『中世の秋』や澁澤氏のほかの著作との関連なども垣間見えてまた興が深い。 今もって早世の惜しまれる御仁であります。
Posted by
この本は1961年に雑誌『みづゑ』に連載されていたもので、ずーっと澁澤が出版をためらっていたものである。これが刊行されたのは1979年である。澁澤らしくない文体であると評されるこの本は、私が思うに書斎のダンディーこと澁澤自身が指向したかった悪の真意とは《hypermoral 超道...
この本は1961年に雑誌『みづゑ』に連載されていたもので、ずーっと澁澤が出版をためらっていたものである。これが刊行されたのは1979年である。澁澤らしくない文体であると評されるこの本は、私が思うに書斎のダンディーこと澁澤自身が指向したかった悪の真意とは《hypermoral 超道徳》であり、悪そのものではなかったが故に、悪をそのまま額面的に捉えてしまったこの本はバタイユ・バルトルシャイティスを根幹とするうちに翻弄され、自身を見失ったことを『若書き』と評して照れたのかもしれない。
Posted by
- 1