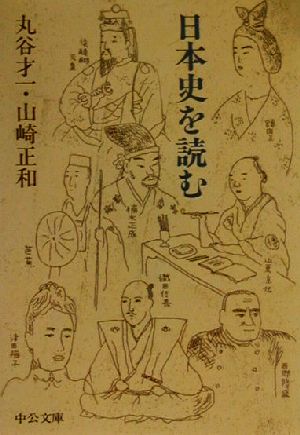日本史を読む の商品レビュー
恋と密教の古代、院政期の乱倫とサロン文化、異形の王とトリックスター、足利時代は日本のルネッサンス、演劇的時代としての戦国・安土桃山、時計と幽霊にみる江戸の日本人、遊女と留学女性が支えた開国ニッポン、近代日本 技術と美に憑かれた人びと 各時代を著した書籍を基に、碩学二人が歴史論を展...
恋と密教の古代、院政期の乱倫とサロン文化、異形の王とトリックスター、足利時代は日本のルネッサンス、演劇的時代としての戦国・安土桃山、時計と幽霊にみる江戸の日本人、遊女と留学女性が支えた開国ニッポン、近代日本 技術と美に憑かれた人びと 各時代を著した書籍を基に、碩学二人が歴史論を展開する 非常に濃密な内容で、飽きる暇がない 知識の海の深さに脱帽する
Posted by
文学者の語る古代史は面白い。 恋愛を大っぴらにして顰蹙を買われないという古代人のおおらかさ、基本的に色恋沙汰に寛容であった日本人が明治を境に変化するのは、欧米の思想が定着し、国民国家としての自覚、それは欧米を常に意識したものだったが、の目覚めによるものなのか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
万葉集~現代に至る37冊の本から日本の歴史の根源を読み解くという、従来の歴史ではとても学べない小説家と劇作家の「知の巨人」による歴史対談。 400ページというそれなりのボリュームのある本だが、読めば読むほど興味の渦に巻き込まれ「至福の時間を浮遊する」ような錯覚に陥り、もっと本の分量を多くして欲しいと思うほどである。 今年読んだ本の中で一番面白い本だった。 まず、前書きで、日本の歴史は、日中関係というより、日中関係の不在がより多く日本を作っていたという事実の再発見ということから始まり、冒頭からその面白さに引きずり込まれる。 具体的な例を挙げると、 日本の恋愛文化 ○日本には恋愛文学の脈々たる伝統があるが、中国は恋愛心理への関心が乏しく、個人への長寿への強烈な執着があった。両者にはその違いの自覚もなくそれぞれの歴史を辿り、西洋のような民族を超える世界文明が生れなかった。 ○日本文化は朝鮮の渡来民のもってきた儒教的なものを、本質的なところでは排除しつづけた。 一番決定的なものは、恋歌中心の文化。儒教文化からみれば恋愛詩は非常な劣位にあって権威のあるものじゃない。恋愛というものは公に認めるわけにはいかないものだった。ところが日本文化はそれを大々的に、しかも天皇家を中心として認めつづけたわけです。 中国を超えた普遍的なものというのは、日本の場合、色欲の肯定、恋愛文化ですね。その点では西洋文化にかなり近かった。 天皇と上皇との関係、および藤原家との関係 ○祭司王の「祭司」のほうは天子に任せ、もっぱら「王」のほうを担当しようとしたのが上皇でした。 ○「万世一系」というよりは「藤原家」との「万世二系」といった関係が「大化改新」以来千年間続いた。これが意外に日本史のいろんな性格を決定しているし、ひょっとすると日本文化の根底を決めているんじゃないかという気がする。 藤原家としては、古代的司祭のー政治的に言えば権威の部分を天皇に持ってもらって、自分が権力でありたいと考える。ところが天皇家はそれでは納得しない。そこで自分を権威(天皇)と権力(上皇)の二つに分けることで、藤原家と対立しようとする。 この構造が一つの循環をなして日本文化の根底を作った。 日本人の政治思想には、統治というのは権威と権力の二重構造を持っていなければならないという謂わば立憲君主と総理大臣のような関係をつくるほうがいいという、近代的な感覚がどこかにあった。 等々、このような二人の遣り取りが近代史に至るまで続き、興味が尽きない。
Posted by
古代から現代までを8つの章を立てて丸谷才一と山崎正和が対談する。2人とも学識深く、独自の歴史観も持っておられるので、興が尽きない。特に、平安時代と南北朝のお話に聞き入りました。美味しいお酒と肴を用意して、こんな大人の談論風発ができれば、人生は豊かで楽しいものでしょうね。
Posted by
37冊の本を紹介しつつ、日本の歴史を彩った人物やエピソードについて、丸谷才一と山崎正和の2人が語り合っている本です。 それぞれ小説家と劇作家としても多くの業績を残している2人だけあって、とくに文化史の領域において想像力を交えながら日本の歴史の中に大胆な補助線を引くようなスケール...
37冊の本を紹介しつつ、日本の歴史を彩った人物やエピソードについて、丸谷才一と山崎正和の2人が語り合っている本です。 それぞれ小説家と劇作家としても多くの業績を残している2人だけあって、とくに文化史の領域において想像力を交えながら日本の歴史の中に大胆な補助線を引くようなスケールの大きな議論が展開されています。ときに大風呂敷に見えてしまうのも事実ですが、その欠点を補って余りある豊かな精神史的文脈が次々に掘り起こされていく話の展開がたいへんスリリングです。 そうした意味で、歴史のおもしろさに触れることのできる本ではないかと思います。
Posted by
大半の言説は、作家、劇作家の想像力と「思い込み」の産物ではないか?という疑問をほの抱きつつも、プロの歴史家でもなんでもない身としては、ひたすら面白く、かつ、両巨頭の博識とケレンに畏れ入る、という仕掛け。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
う~む、なんだか難しくて良くわからなかった。歴史本を選択し、これをもとに丸谷氏と山崎氏が歴史対談をするのだが、読んでみようかなと思った本は『影武者徳川家康』ぐらいかな。江戸時代末期、からくり師から生まれた時計師の田中久重という人が、その後佐賀藩に呼ばれて船のエンジンを作り、田中製作所になり、三井の資本が投入されて東芝になったという話は初めて知った。日本では庶民も時間を意識した生活をしていたのに、それを支えるハード(時計)ときたら、線香から日時計止まり。つまりソフト先行型。機械時計が普及した後に公共時間の意識が発達した「すべての道はローマに通じる」で象徴される、ハード先行型の西洋とは逆、というのは面白い。
Posted by
知識量が半端じゃない蘊蓄がすごい あっちに飛ぶかと思えばひらりとこちらへ 嬉しかったのは「隆さん」の本を取り上げていてよい本だと。 うんうん、あれは面白いのですよ。ほんとに。
Posted by
- 1