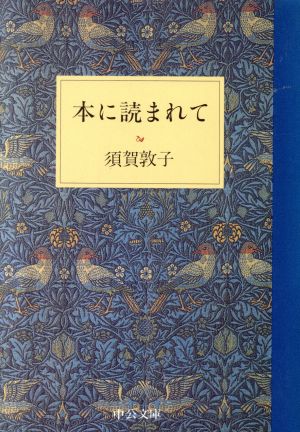本に読まれて の商品レビュー
須賀さん2冊目。 旅の途中で。言葉が文章が美しい。 読んでみたい作品が増えた。普段読まないような本を読みたくなったらこれに頼る。
Posted by
著者の本好き・読書好きが伝わる一冊。 半ばエッセイのような書評は「この本のここがとてもいい!」「この本に出会えてよかった!」という感動・感嘆を隠すこと無く、本物の教養や知性に裏打ちされた文章で綴られている。その本の不満足な点も述べていることもよい。ネタバレにならず、読者の読書欲...
著者の本好き・読書好きが伝わる一冊。 半ばエッセイのような書評は「この本のここがとてもいい!」「この本に出会えてよかった!」という感動・感嘆を隠すこと無く、本物の教養や知性に裏打ちされた文章で綴られている。その本の不満足な点も述べていることもよい。ネタバレにならず、読者の読書欲を煽り、文章自体が読み物としておもしろいーー書評のお手本と言えよう。
Posted by
須賀敦子のスクリーニングを経た書物であれば、ぜひとも読んでみたいという本があるわけで、さっそく2冊の本を注文した。著者が無類の本好きであったということがしみじみと伝わってくる。
Posted by
カフェでおばさまたちが「あなたまだ須賀敦子読んだことないの? とても素敵なかたよ」という会話をしていて自分も混ざりたかった、という話を知り合いに聞きました。 須賀敦子の「素敵さ」とはどこからくるんだろう。彼女の知性と教養のある文章は、読む側のレベルまで一段高いところに上げてくれ...
カフェでおばさまたちが「あなたまだ須賀敦子読んだことないの? とても素敵なかたよ」という会話をしていて自分も混ざりたかった、という話を知り合いに聞きました。 須賀敦子の「素敵さ」とはどこからくるんだろう。彼女の知性と教養のある文章は、読む側のレベルまで一段高いところに上げてくれるような気がしてしまいます。 『本に読まれて』は須賀敦子が亡くなった1998年初版の書評集。 ウィリアム・モリスの表紙は素敵だけど、生きていたら彼女が表紙に選んだかどうか。 (最初のエッセイ『ミラノ 霧の風景』の出版が1990年だから、彼女が名エッセイストとして知られた期間はじつはすごく短い。没年の1998年には一気に4冊の本が出版されています。) 掲載されているのは88年〜95年くらいまでの書評や解説、読書日記など。 私が読んだことがあるのはデュラス『北の愛人』、川端康成『山の音』、タブッキぐらい。 ポール・ボウルズ、E.M.フォースターなど、須賀敦子は「楽しく読んだ」くらいに書いてますがなかなかレベルの高い名前が並びます。 没後にあわててまとめた感が多少ありますが、「湊千尋という写真家」とか山崎佳代子といった名前が新鮮さをもって書かれていたり、生前から親交があったのだと思うがのちに須賀敦子関連の本を出している大竹昭子、松山巖、池澤夏樹の名前があがっているのも興味深い。 以下、引用。 仕事のあと、電車を降りて、都心の墓地を通り抜けて帰ることがある。春は花の下をくぐって、初冬のいまはすっかり葉を落とした枝のむこうに、ときに冴えわたる月をのぞんで、死者たちになぐさめられながら歩く。日によって小さかったり大きかったりするよろこびやかなしみの正確な尺度を、いまは清冽な客観性のなかで会得している彼らに、おしえてもらいたい気持ちで墓地の道を歩く。 ポスト・イットなどという、糊のついた便利なしおりがまだ市販されていなくて、じぶんで細く切った白い紙に、要点やら感想を書き入れたのが、降伏の旗のようにあちこちにはさんである。 「多くのものが教会のそとにあります。わたしが愛していて捨てたくないと考えている多くのもの、また神の愛する多くのものがそのそとにあります。神が愛するのでなければ、それらのものは存在しないはずだからです。」 こんなちっぽけな、こんな思想のない建物で暮らしていたら、きみたちはこれっぽっちの人間になるぞ。建物が人間を造るということを、よくおぼえておきなさい。 「彼女(ハエは女性名詞だから)が死ぬのを見るために、私はそばまで行った」 「私がそこにいることが、その死をよりむごたらしくしている。それをわかっていて、私はそこにいた。見とどけるために。死がどんなふうにハエをなめつくすかを、そして、どこから、たとえば外部からか、壁の厚みからか、地面からか、その死のやってくる場所を見とどけたかったから」 そしてハエは死ぬ。作家は時計を見る。三時二十分。 「彼女の死を正確に記すことによって、ハエはひそかな葬儀をしてもらったことになるのだ」 若いときに読んだといっても、なにも理解していなければ、読んでないに等しいのではないか。いや、読んだと思っていばっている分だけ、マイナスということだ。 絵本に夢中になって、ゴハーンと呼ばれても聞こえない子供みたいに私はこの小さな本に没頭し、読んだあとも、また開いては写真や挿画を眺めた。 いつか時間をつくって、もういちどサン・ドニに行ってみよう。もういちど訪ねて、わけもわからずに、中世のキリスト教に捉われていた自分を、あの王たちの寝姿を見ながら、もういちど考えてみよう。やがては迎えなければならない、自分の死までの道がすこしは見えるかもしれない。 「この戦争のひとつの特異な点は、文化財の徹底した破壊にあると思う。なぜ兵士が閉じ籠っているわけでもないカトリックの教会やイスラム寺院が、片端から爆撃されなければならないのだろう。……なぜ市立図書館みたいな戦略上、何の意味もない建物が焼き打ちにあっているのだろう。……つまりひとつの土地の集合的記憶の抹殺が、最初から〔この戦争の〕目的だったのではないだろうか」
Posted by
やわらかさの中に強さと対象への愛情のある文体が須賀敦子の魅力。こういう文章を書ける人がもうこの世にいないということがとても残念でならない。世界の歴史や政治や文学にまったくと言っていいほど知識がなく、ほとんどの作家名を覚えられないわたしでも楽しく、時には感動で深いため息をつきながら...
やわらかさの中に強さと対象への愛情のある文体が須賀敦子の魅力。こういう文章を書ける人がもうこの世にいないということがとても残念でならない。世界の歴史や政治や文学にまったくと言っていいほど知識がなく、ほとんどの作家名を覚えられないわたしでも楽しく、時には感動で深いため息をつきながら読んだ。「バスラーの白い空から」の書評の冒頭は解説にも触れられているが、この冒頭を読むだけでも物凄い人だな、須賀敦子はと思うことができる。 旅の途中で読んだとか、床の上で読んだとか、どういうときに読まれたものなのかが(エッセイ形式だからか)細かく記述されているためその状況に思いを馳せて、書評される本の雰囲気や質感などもじっくり思い描くことができる。 書評なのにエッセイの形式をとっている謎は解説で明らかになる。
Posted by
須賀敦子は文章がむちゃくちゃうまい。書評であっても、紹介する本の引用を飲み込んで書評の文章そのものが1つの世界観を紡ぎ出すことあるんだなという驚き。幻想的で、すらりとした描写は読んでいて物思いを想起させる。 「パウル・ツェラン全詩集」「手にとって、ぱらぱらとページをめくったとた...
須賀敦子は文章がむちゃくちゃうまい。書評であっても、紹介する本の引用を飲み込んで書評の文章そのものが1つの世界観を紡ぎ出すことあるんだなという驚き。幻想的で、すらりとした描写は読んでいて物思いを想起させる。 「パウル・ツェラン全詩集」「手にとって、ぱらぱらとページをめくったとたんに、深く引き込まれてしまうような書物に出会うことは、めったにない。」という著者が珍しく引き込まれた本。 海外の詩が訳される意味、特にツェランのような日常と硬く対立したところで造られた詩が、訳されたことの意味は非常に大きいという。
Posted by
書評集。文章に著者の知性と教養がにじみ出ている。そして、著者が本との出会いを大切にしていることがよく伝わってくる。
Posted by
須賀敦子さん、ずっと気になっていた。何から読もうか、須賀敦子という名を目にするたびに考えていたんだけど、書店で目にしたこちらの装丁がすごくツボだったし、書評好きなので購入した。 比喩に理念が絡まっていて(一読では美しいけれども見逃しがち)すごくかっこよくてあたたかい文章だった。...
須賀敦子さん、ずっと気になっていた。何から読もうか、須賀敦子という名を目にするたびに考えていたんだけど、書店で目にしたこちらの装丁がすごくツボだったし、書評好きなので購入した。 比喩に理念が絡まっていて(一読では美しいけれども見逃しがち)すごくかっこよくてあたたかい文章だった。 還暦超えてもデュラスにときめけるのか、ちょっと長生きしたいななんて思った。
Posted by
大好きな須賀敦子さんの書評集なるものがあると聞いて借りてきた。思えば最初に教科書か何かで須賀敦子の文章に触れ、短い章の中に生半可なるものを感じ手に取ったのが「遠い朝の本たち」というこれも須賀さんの小さなころの読書体験を綴った本だったと思う。 静謐な中にも人生への暖かで豊かな眼差し...
大好きな須賀敦子さんの書評集なるものがあると聞いて借りてきた。思えば最初に教科書か何かで須賀敦子の文章に触れ、短い章の中に生半可なるものを感じ手に取ったのが「遠い朝の本たち」というこれも須賀さんの小さなころの読書体験を綴った本だったと思う。 静謐な中にも人生への暖かで豊かな眼差しに溢れた須賀さんの文章は読んでいると自分の身体が浄化されていくような気すらする。本作は色々な雑誌に須賀さんが寄稿した書評を集めているのだが、これが「只の書評ではない」のだ。数行で人の心を掴む静かで正確な筆致。例えばこうだ。 「仕事のあと、電車を途中で降りて、都心の墓地を通りぬけて帰ることがある。春は花の下をくぐって、初冬のいまはすっかり葉を落とした枝のむこうに、ときに冴えわたる月をのぞんで、死者たちになぐさめられながら歩く」 佐野英二郎の「バスラーの白い空から」という本の書評の書き出しなのだが、およそ書評の書き出しとも思えないむしろエッセイのそれだ。しかし実際にこの後に続く文章を読んで、この本を入手してしまったということからも書評としての強度も備えているということなのだろう。軽々と時空を越えていくこのエッセイ的書評集を読んだ後では、なにより須賀敦子の本をまた読みたくなってしまった。
Posted by
人に本をすすめるという難業を かろやかに文章に乗せている いつかその本に出会えるような余韻たっぷりに
Posted by
- 1
- 2