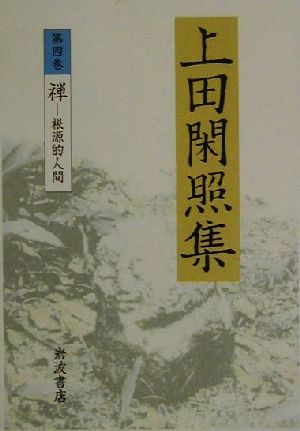上田閑照集(第4巻) の商品レビュー
『講座・禅』(全8巻、筑摩書房)に収録された著者の論文などが収められている。西田幾多郎の参禅についての考察や、道元の「普勧座禅儀」の解釈に関する議論もあるものの、禅の事柄を仏教学的な観点からではなく人間の根源的な事柄として捉えなおす議論が中心を占めている。 著者は哲学的人間学の...
『講座・禅』(全8巻、筑摩書房)に収録された著者の論文などが収められている。西田幾多郎の参禅についての考察や、道元の「普勧座禅儀」の解釈に関する議論もあるものの、禅の事柄を仏教学的な観点からではなく人間の根源的な事柄として捉えなおす議論が中心を占めている。 著者は哲学的人間学の立場から出発しながら、その底を踏み破ることによって禅の立場へ出ようとする。直立歩行によって、人間は手を用いて外に働きかけ、環境を自由に作り変えることができるようになった。座禅とは、そうした人間が手足を組んで、外に向けての働きかけをいっさい絶つことであり、それによって自己の内へと返ることである。 著者は、こうした座禅の中にある人間が「自由」だと述べる。ただしそれは、自己決定性や自発性ということとはちがう。手足を組んで「何もしない」ということが、かえっていっさいの「とらわれ」から脱却して「自由」であるという意味である。 こうした「自由」は、具体的な状況から逃げ出すことでもなければ、具体的な問題を解決してくれる特効薬でもない。著者のあげている例によると、イライラしているときにあえて座禅をすることで、イライラが改称されるわけではない。イライラしている自己がイライラしているままで、イライラでないものに包まれるという事態を現生させるのである。それは、具体的な状況の中で具体的な問題に突き当たっている自己が、そのままで無から出なおすということである。 一人で自己の内へと立ち返る座禅から、「人と人」が相対する参禅へ、そして日常へ、という連関は、座禅によって現生する「限りない開け」に包まれたままで、日常を生きることを表わしている。その上で著者は次のように述べる。「日常工夫とは、結局、一日一日をどういう仕方でか坐禅をし、坐禅から立って人に出会い人と交わり、物事にかかわり、そして坐禅に還る、ということである。それでどうなるという問題ではなく、ただそのような生き方をするということに尽きるであろう」。
Posted by
- 1