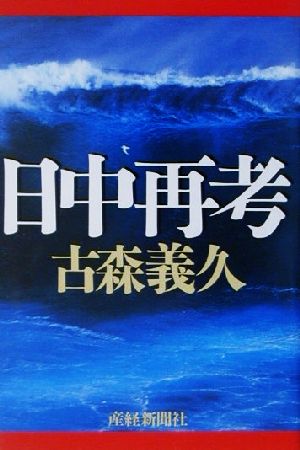日中再考 の商品レビュー
(2004.04.30読了)(2003.05.18購入) 1998年12月から2000年11月まで産経新聞の中国総局長を務めた著者の日中関係についての報告である。産経新聞は、台湾に支局や特派員を置く日本のマスコミには中国本土の特派員常駐を認めないという中国政府の要求を呑まなかった...
(2004.04.30読了)(2003.05.18購入) 1998年12月から2000年11月まで産経新聞の中国総局長を務めた著者の日中関係についての報告である。産経新聞は、台湾に支局や特派員を置く日本のマスコミには中国本土の特派員常駐を認めないという中国政府の要求を呑まなかったために1998年まで特派員の駐在を認められていなかった。この年に台湾支局を現状のままで駐在を認められた。 この本では、中国側による日中友好なるものの異様さが述べられている。 田中角栄首相が訪中し日中共同声明に調印したのが1972年9月29日である。1978年8月12日に日中平和友好条約調印が行われている。(このときの首相は福田赳夫) 日中友好を報じるとすれば1978年以降の日中間の交流について報じるというのが常識的な行き方ではないだろうか。ところが、1999年の小渕恵三首相の訪中の直前には、「日本侵略特集」が報じられ、2000年の河野洋平外相の訪中の直前には、「南京大虐殺」の油絵の写真が掲載された。これで日本からの訪問者を歓迎して、友好を促進しようということになるのだろうか。国交が回復して20年以上過ぎているのに。 このような、中国側の姿勢についてAP通信のマーティン・ファクラー記者は 「中国共産党の最大の歴史的偉業は、侵略者の日本を打ち破り、祖国を解放したことである。その偉業は、共産党が永遠の一党支配政党として、すべての権力を独占する統治の正当性の主要な支柱となる。」 「共産党が統治の正当性を国民に確実に認識させつづけるには、国民に抗日の偉業、特に闘争相手の日本軍の残虐行為に脚光を浴びせ続けなければならない。」 と報じている。的を射た見方だと思う。 毛沢東、周恩来、鄧小平らがいなくなり、いるだけでまとめることができた時代が終わったということもあるのだろう。 日本の政府開発援助(ODA)が過去二十年余、北京の近代都市としての経済や社会のインフラ建設に、驚くほどの額、投入されてきた。1980年以来の、北京の都市づくりに供与された日本の援助は、合計すれば約4千億円に上る。だが北京市民はその事実を知らない。日本でもまず話題とはならない。(中国に供与されたODAの総額は2000年までで3兆円ほどとなる。) これほどことをしていながら反省がない、償いがないといわれ続けている。 援助の結果、日中間の貿易は拡大し、1999年には、661億ドルを記録した。貿易収支は、日本の輸入超過で、1999年には200億ドルの貿易赤字、2000年には250億ドルにまで増加した。これでもまだ援助を続けるの? そのほかにも数々の日中関係の不思議が述べられている。 著者 古森 義久 1941年 生まれ 慶応大学経済学部卒業 毎日新聞社社会部記者 1987年 産経新聞社入社 (「MARC」データベースより)amazon 日本への憎しみと恨みを徹底的に教え込む教育。ビジネス現場に出回る日本製品の模造品と、日本企業に対する当局公認の債務不履行。日本人が感じている親しみとは裏腹の中国の実態にメスを入れる。『産経新聞』連載を単行本化。
Posted by
中国の日本に対する感情の実態についてのレポートで、読めば読むほどに、中国の教育やビジネスの異様さが伝わってくる。中国では、幼いころから南京大虐殺などの日本の負の面のみをクローズアップしてイメージに刷り込んでいるという。それでいて日本には援助金を出させるだけ出させて、その実、決して...
中国の日本に対する感情の実態についてのレポートで、読めば読むほどに、中国の教育やビジネスの異様さが伝わってくる。中国では、幼いころから南京大虐殺などの日本の負の面のみをクローズアップしてイメージに刷り込んでいるという。それでいて日本には援助金を出させるだけ出させて、その実、決して日本を許そうとはしない。中国というのはあらゆる意味で特殊で、その上日本にとっては関わりの深い国だけれど、両国の間にはこの先、本当の友好というのはおとずれないのではないかと、ちょっと暗い気持ちになってしまった。 中国でのリース事業で得た最大の教訓は、この国のビジネスではどんなことでもすべて自分で最後まで確認しないとなにが起きるかわからない、相手を決して信用できない、ということですね。現代ビジネスで、これだけはどんなことがあっても履行されるだろうと当然視することが中国市場ではできないのです。(p.81)
Posted by
- 1