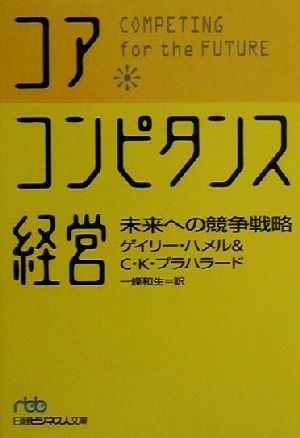コア・コンピタンス経営 の商品レビュー
「コア・コンピタンス…
「コア・コンピタンス」という言葉を提唱したハメル・ゲイリーの文庫本である。企業経営を考える意味で、基本となる戦略本であり、常に手元において何度も繰り返して読んでみたい本である。
文庫OFF
2024年では考えられないような、日本企業を成功例として説明されている内容で、時代の差を感じます。 しかし、書かれていることは現在であっても真理と思える内容。一方で革新的な内容とも思います。 例えばいまだにプロダクトアウトかマーケットインかという議論がなされ、メーカーではプロダク...
2024年では考えられないような、日本企業を成功例として説明されている内容で、時代の差を感じます。 しかし、書かれていることは現在であっても真理と思える内容。一方で革新的な内容とも思います。 例えばいまだにプロダクトアウトかマーケットインかという議論がなされ、メーカーではプロダクトアウトを悪のように捉える風潮を感じます。そうではなく技術や運用能力の束となるコアコンピタンス先導で未来を作っていくべきというのが本書で書かれています。 製品を作るのではなく、企業にかかわる未来の構造を作るには、という観点の本で、わたしにとっては稀有な本でした。良著
Posted by
経営の古典的名著だが、翻訳本特有の読みづらさがある 他社にはないコアコンピタンス、で未来を見据えよという主張 「競争力をもつ会社は競争に勝つ」というトートロジーの問題もあるのでは?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
コア・コンピタンス経営 ・自社ならではのスキル・技術を強化し、未来の競争を勝ち抜く ・10年後の業界と顧客の姿を思い描き、自社ならではの競争力を活かす ・目先の利益を求めるより、未来を創出することの方が重要 ■なぜ優良企業が衰退するのか ・加速する業界の変化についていけなかった結末 ■業界の変化に対応するためには ・基本戦略を練り直し、流通チャンネルや顧客など会社の基本思想を再検討 ・基本戦略の練り直しや10年後の顧客ニーズの予測など根本的な見直しがなければ未来はない ■未来の競争に勝つために ・過去の何を会社の強みとして活用すべきか ・もはや役に立たない過去の遺物はないか ■どうすれば未来を展望できるか ・まずは未来をイメージし、子供のように先入観を捨てて考える。 ・ライフスタイル・人口構造など深く洞察 ■既存の市場の枠を超える ・既存の狭い市場ではなく、「機能」に焦点を当てる ・従来の機能を新しい手段で実現する (黒板の機能:少人数で情報をリアルタイムに共有する事 →黒板から情報を引き出すのは難しい。黒板メーカーではなく電機メーカーがコピースキャナー機能で実現) ■会社の未来をイメージする ①5年後、10年後にどのような新しい付加価値を顧客に提供するべきか ②その付加価値を顧客に提供するために、どのように顧客との接点を作り変えていかなければならないか ③これからの数年間、どのように顧客との接点を作り変えていかなければならないか 未来への視点とは、 ・付加価値 ・企業力 ・顧客との設定んについての見方 ■コア・コンピタンスとは何か ・顧客に特定の利益をもたらす一連のスキルや技術 (ソニーにとっては携帯性、コアコンピタンスは小型化) ・製品単位ではなく、それらを束ねた物である。 (宅配便のパッケージ経路・集配のコアコンピタンスは、バーコード技術・無線通信・ネットワーク管理・線形計画などのスキルの統合) ・コア・コンピタンスはどんな製品やサービスよりも上位に置かれる存在 ・どんなサービスより寿命が長い ・競争力の根源で、個々の製品やサービスは果実である。 ・コアコンピタンスを大事に育てることによってしか企業の存続は望めない
Posted by
20年前の書籍だが、現在でも十分に通用する考え方でさある。特に日本企業の考察は、現時点の日本企業と比較すると悲しくなる
Posted by
研修の課題図書の参考図書に書かれていたのをブックオフで見つけたので読んでみた。 企業の強みを表すコア・コンピタンス。当たり前の言葉のように使われていたけど、改めてその意味を学習。 他社には提供できないような利益を顧客にもたらすことのできる、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の...
研修の課題図書の参考図書に書かれていたのをブックオフで見つけたので読んでみた。 企業の強みを表すコア・コンピタンス。当たり前の言葉のように使われていたけど、改めてその意味を学習。 他社には提供できないような利益を顧客にもたらすことのできる、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合体。 俺が学生の頃に書かれ、社会人になってすぐに文庫化された本だけれども、中に書かれている事例が古くなってはいるものの、未来への変革を考えるには今でも大切なことが書かれていたと思う。
Posted by
もはや古典の域に差し掛かっているが、コア・コンピタンスという考え方自体は、時代にかかわらず、普遍的なものであるとわかる。
Posted by
今となっては古典に分類されるであろう1995年発刊の経営戦略本。今2017年に読んでみて、内容に陳腐さを感じるようなところがない。というか、40代以上だと過去のあるあるが一杯出てきて懐かしくも、その裏で行われていた企業間の競争を垣間見えて楽しく読めると思うし、それ以下の世代も企業...
今となっては古典に分類されるであろう1995年発刊の経営戦略本。今2017年に読んでみて、内容に陳腐さを感じるようなところがない。というか、40代以上だと過去のあるあるが一杯出てきて懐かしくも、その裏で行われていた企業間の競争を垣間見えて楽しく読めると思うし、それ以下の世代も企業間の競争の歴史を知る上で役に立つと思う。1995年当時と以前の米国および日本企業のケースを通じて、未来に勝つために何をしていくべきなのかについての解説が、戦略本によく有りがちなフレームワークの解説ではなく、ケース企業の来し方を見ていくスタイルで読みやすい。教えてくれるようなものではなく、道標が提示され、自分で考えたければ考えれば程度なので、気軽に読み流せる。 題名にあるコア・コンピタンスってなに?というと、「顧客に特定の利益をもたらす一連のスキルや技術」とのことで、非常に多くの企業名が出てくるが、一例としては、以下の様なものが提示される。 企業、顧客利益、コア・コンピタンス ソニー、携帯性、小型化 フェデックス、提時配達、物流管理 EDS、シームレスな情報の流れ、システム統合 ホンダ、燃費・加速・低騒音・低振動、エンジン IBM、顧客ニーズと同社技術の重要な仲介役、セールスマン 恐らく、この本で一番名前が出てくる企業はIBM。それまでのIT領域での強大な力が、新しい市場形成の波に乗り遅れ、マイクロソフトとインテルに敗れ低迷していくところのストーリは、この本の出版のあと復活したと称される企業が、またもやクラウドの波でアマゾンに一敗地にまみれているように見える現状と重なって見えて、この状況が何によるものなのかまで思考させてくれる点が面白かった。 著者は、ゲイリー・ハメル。経営思想家という肩書らしいが、ロンドン・ビジネススクール客員教授とか、国際コンサルティング会社ストラテゴスの創設者などの肩書を持ち、経営に関する書籍を他にも出している。 この本の想定読者は、実務を経験ずみの中堅社員以上といったところか。戦略のフレームワークを知りたい場合は、この本よりも、ポーター本等で5Forces分析やSWOT分析等について学ぶと良いかもしれない。
Posted by
経営幹部は、2~5割の時間を、社内問題にとらわれず、未来を考えるために積極的に使わなければならない。5~10年後「将来、あなたの会社が対象とする顧客は誰だろうか?」「将来、あなたの会社の競争優位の源はなんだろうか?」「将来、あなたの会社の独自性はどのような能力からくるだろうか?」
Posted by
よい、良いけど長い。古い本なので例示などがわかるようなわからないようななので、少し端折った短いものがあるとなおよいかな。
Posted by