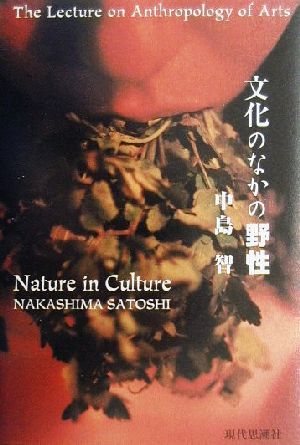文化のなかの野性 の商品レビュー
自身の〈直観〉(「私の直観の仮初の姿[p9]」「自分でもわからない直観によって[p126]」など)を大切に主に民俗学的なアプローチ(芸術人類学)で究明する作家。講義録をもとにしているので[p8]、本では表現できない部分(漏れてしまうこと、ディスコミュニケーション[p121])も?...
自身の〈直観〉(「私の直観の仮初の姿[p9]」「自分でもわからない直観によって[p126]」など)を大切に主に民俗学的なアプローチ(芸術人類学)で究明する作家。講義録をもとにしているので[p8]、本では表現できない部分(漏れてしまうこと、ディスコミュニケーション[p121])も?ライフヒストリーによると[p372-]四歳で自殺未遂、小学生で「真実など無くて、それぞれの立場や視点だけが有る」という結論に至り、その後の創作活動などで「世界に陶酔することで、世界と合一した身体が笑い始める」という経験を(パフォーマンスをとおして?)したり、作家などとの交流のなかで「目に見えるものすべて完璧」というスタンスに至ったり。シャーマニズムやスーフィズムなど、それだけをいうと一般的にはいかがわしいとかネガティブなイメージがまとわりついているものに感応していたり、読み手に伝わるか伝わらないかギリギリの(〈直観〉に注意深く選ばれた)言葉遣いだったりで、広範な読者層は無理かも。「民俗学」とはいったが、「人類学」「~学」「アート」などというような枠組みで考えたり解釈するのではなく、体感すべき。ドローイングを徹底的にして栄養失調になったり[p17]、グラナダの坂道を歩いたり[p193]。また、「行」(陶酔の行?[p14])の方法で、どこにも焦点を合わせないで見るなど具体的な方法も。講義録だからか、「共同幻想」などことばが唐突に出てくるが、学問領域とアート領域のあいだの初々しい合一と新生。
Posted by
- 1