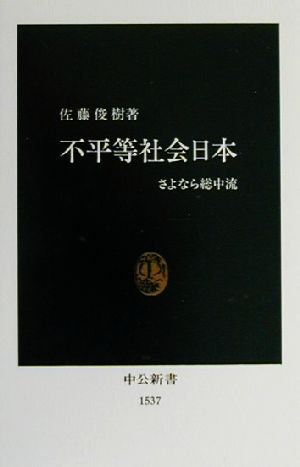不平等社会日本 の商品レビュー
日本の階級社会の現状…
日本の階級社会の現状を、豊富なデータを踏まえて述べている。自己責任の虚しさがわかる。
文庫OFF
1 95年SSM調査における「資源配分原理(現実/理想)」に関する質問(回答は実績・努力・均等・必要):理想は努力主義だが、現実は実績主義。ホワイトカラー被雇用上層で実績主義、つまり努力すれば何とかなるという意識。ただし実際には父親の学歴と本人の学歴に関係がありそう。自営業では努...
1 95年SSM調査における「資源配分原理(現実/理想)」に関する質問(回答は実績・努力・均等・必要):理想は努力主義だが、現実は実績主義。ホワイトカラー被雇用上層で実績主義、つまり努力すれば何とかなるという意識。ただし実際には父親の学歴と本人の学歴に関係がありそう。自営業では努力主義。 2 「世代間(職業)移動」についてオッズ比などを見ると、日本は階級のない、開かれた(選抜)社会になっている(新中間大衆論:村上泰亮)ように見えるが、しかし、W雇上の経路依存性(若い頃はみなW雇下)を考慮して計算すると、団塊世代以降で戦前の閉鎖性に戻っている。 3 (1)W雇上の再生産の潜在化、(2)ホワイトカラー/ブルーカラー境界の横断、(3)ブルーカラー雇用から自営への上昇ルート…戦後の開かれた社会(可能性としての中流)を形成した要因→団塊の世代以降急激にW雇上が閉鎖化 4 「団塊の世代」以降の知識エリート、W雇上…1 力のおよばない範囲まで「実績」にしてしまう 2 その「実績」は既得権へと曖昧化される 3 エリートの自己否定を強いられる
Posted by
どうもすっと頭に入ってこない本だった。なぜだろうと考えたが、2000年という時期の意外と古い本であることが今の実感とリンクしなかったからかもしれない。また、SSM調査のみに依存した分析というのも少々ひっかかる。できれば、他の調査も引用して、この分析の確からしさを高めて欲しかったと...
どうもすっと頭に入ってこない本だった。なぜだろうと考えたが、2000年という時期の意外と古い本であることが今の実感とリンクしなかったからかもしれない。また、SSM調査のみに依存した分析というのも少々ひっかかる。できれば、他の調査も引用して、この分析の確からしさを高めて欲しかったと思う。最後の統計の解説は親切と思うが、途中にコラムの形で散在させても良かったのではないかと思った。
Posted by
ブルデューの論じた文化資産による階層の再生産を、戦後日本の社会調査に基づいて実証的に論じています。 日本社会は戦後になって、メリトクラシーが全面的に行き渡ることになりましたが、実績主義の中に入り込んでいる機会の不平等が目に見えなくなってしまったことを、著者は説得的に示しています...
ブルデューの論じた文化資産による階層の再生産を、戦後日本の社会調査に基づいて実証的に論じています。 日本社会は戦後になって、メリトクラシーが全面的に行き渡ることになりましたが、実績主義の中に入り込んでいる機会の不平等が目に見えなくなってしまったことを、著者は説得的に示しています。 結果の平等原理に基づく社会では、一人ひとりの持つどのような背景がどの程度有利・不利に働くのかということは、後になってからでないと分からないと著者は言い、それゆえ結果の平等がどの程度実現されているかをつねにチェックし、その不公正を事後的に補償できる仕組みをあらかじめ用意しておかなければならないと、著者は提言しています。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本は「努力すればなんとかなる」と「努力しても仕方ない」の二重底から成り立つ。かつては個人の責任か集団の責任か問われなかったが、それが崩壊した。 評価は「実績」に依るべきだとする人は年収と相関するが、それは主にホワイトカラー雇用上層(年功序列下)である。また、実績主義は父の学歴とも因果関係にある。これは近年加速している。 親と子の職業が違う(管理職が平になってる)のは年功序列を考えると当然。W雇上は、流入が多いから少し変動しているにすぎない。事実、40歳時点でのW雇上の父を見ると、同職となる傾向がさらに強まっていることがわかる。これは戦後の経済成長で高まった開放性が、その自体の閉鎖性により覆われたということである。 階級再生産は「なって当然」の世界であるために、階級における責任感(やりたいこと)を失わせる。しかも、形式上平等のため、なおさら。 敗者の再加熱の仕組みは「選抜機会の多元化」と「選抜自体の意味の空虚化」がある。日本では形式上平等なため、後者。この結果、エリートの責任感をも失わせる。 唯一、B雇上→W雇上ルートの存在が、挑戦の機会を開いてきたが、近頃このルートも閉鎖されてきている 現在の選抜社会の行き詰まりを打破するためには、1.ブルーカラー専門職とホワイトカラー専門職の融合、2.専門職キャリアの再編、3.選抜機会の多元化、4.世代を超えた不公平の緩和がある。 機会の平等は、階級再生産を考慮すると達成しにくいし、この社会に実力の代理指標しかない以上確認しにくい上、事後的にしかわからず、対策が打ちにくい。例えば、学歴を打破する情報リテラシーにも(父の職業に伴う)格差が存在するし、それは後からしかわからない。その中で機会の平等原理を確保するためには、不平等の監視と、事後的な不平等の保障が必要になる。 学歴に変わる指標として、市場はまだマシなのではないかと考えている。
Posted by
データの分析の解説が難しくてよく分からなかった。 いまのお嬢様は、親の学歴・職種が資産となっているが自覚が無く自らのステイタスを実績と勘違いしている。
Posted by
「それが「大正世代」「戦中派」「昭和ヒトケタ」と順調に下がっているのが、最後の「団塊の世代」で七.九と反転上昇しており、「大正世代」とほぼ同じ水準で、いわば戦前に戻っている。「団塊の世代」では、父親がW雇上だった人は、そうでない人とくらべて、本人四十歳職では約八倍、W雇上になりや...
「それが「大正世代」「戦中派」「昭和ヒトケタ」と順調に下がっているのが、最後の「団塊の世代」で七.九と反転上昇しており、「大正世代」とほぼ同じ水準で、いわば戦前に戻っている。「団塊の世代」では、父親がW雇上だった人は、そうでない人とくらべて、本人四十歳職では約八倍、W雇上になりやすい。」(p.59)学園紛争は、社会の開放化を反転させる反革命であった。
Posted by
平等とは何か、実績での平等か、努力をみるのか、あるいは最も必要な人に最も与えられるのが平等なのかという問題提起に最初に興味を持ち。真の実績主義と言っても難しくて、機会の平等は事後的にしかわからないというのも興味深い。データ分析は、納得できるところもあれば、そこまで言える?ってとこ...
平等とは何か、実績での平等か、努力をみるのか、あるいは最も必要な人に最も与えられるのが平等なのかという問題提起に最初に興味を持ち。真の実績主義と言っても難しくて、機会の平等は事後的にしかわからないというのも興味深い。データ分析は、納得できるところもあれば、そこまで言える?ってところもあった。
Posted by
統計やグラフやそういうのが何度も出てきて自分にはそんなに不向き、 でも興味のあるテーマなので読みました。 不平等をどう解消しようとかいうよりは、 結局生まれも才能っていう持論を支える材料を一つ手に入れられたみたいなのが大きいかな。
Posted by
最近平等、平等ってたしかによく聞くけど、平等って結局何なのか、どこをめざしているのか、よくわからなかった。そもそも貴族的な社会の不平等を解消するために学歴社会ができたわけで…なのにいまはそれが不平等だという。解決策はあまり納得いきませんでしたが、頭に入ってくる感じがとても心地よか...
最近平等、平等ってたしかによく聞くけど、平等って結局何なのか、どこをめざしているのか、よくわからなかった。そもそも貴族的な社会の不平等を解消するために学歴社会ができたわけで…なのにいまはそれが不平等だという。解決策はあまり納得いきませんでしたが、頭に入ってくる感じがとても心地よかったです。
Posted by