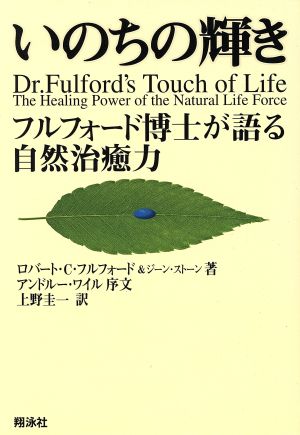いのちの輝き の商品レビュー
吉本ばななと河合隼雄の対談『なるほどの対話』で、吉本ばななが紹介していて気になった本。 使われている表現に、胡散臭さがないでもないけど、一貫して語られる「人間には科学では説明できない側面がある」という説明にはとても共感できたし、「5章 自己管理の秘訣」も、そうだよねと頷けることも...
吉本ばななと河合隼雄の対談『なるほどの対話』で、吉本ばななが紹介していて気になった本。 使われている表現に、胡散臭さがないでもないけど、一貫して語られる「人間には科学では説明できない側面がある」という説明にはとても共感できたし、「5章 自己管理の秘訣」も、そうだよねと頷けることも多かった。「7章 霊性を高める」は、題名の付け方にちょっとびっくりしたけど、自己啓発本を読む感覚で読み進めると、題名の表現の割にそんなに抵抗のあることは書いてないと思う。むしろ生きていく上で大切なことが書いてあるんじゃないかな。 繰り返し出てくる、医師としての患者さんへの姿勢についての記述は、普段医療現場で働いている身として、何度も自分に言い聞かせたいと思う。
Posted by
吉本ばななさんの言う通り、何回も読み直す本となりそう。なんとなく自分の身体で感じてたことをとても的確に言語化されていて、自分の中にたくさんストンと落ちた。忘れそうになったら、また読み返そうと思う。
Posted by
所謂西洋医学とは別のアプローチについて知りたく購入した本。2年ほど放置して、やっと読んだ。人体の捉え方について、漠然と疑問に感じていた部分への言及が多々あり、「やっぱりか〜」という感じ。病気に関して、患者は受け身ではなく当事者、というのは改めてその通りだと(そのように対応する医師...
所謂西洋医学とは別のアプローチについて知りたく購入した本。2年ほど放置して、やっと読んだ。人体の捉え方について、漠然と疑問に感じていた部分への言及が多々あり、「やっぱりか〜」という感じ。病気に関して、患者は受け身ではなく当事者、というのは改めてその通りだと(そのように対応する医師が少ない、という意味でも)。批判につけ霊的な内容につけ、ストレートな言葉で語られ、どこか安心感を覚えた。
Posted by
オステオパシーとは何かがわかる本。日本的に言えば、東洋医学と言ってもそれほど外れていないと思う。アメリカでこういう治療があることに驚くとともに、日本と同様少数派であることに、残念な気持ちとともに、ある種の納得も感じた。商業主義への対抗はなかなか難しいと。最期のほうでは、アメリカで...
オステオパシーとは何かがわかる本。日本的に言えば、東洋医学と言ってもそれほど外れていないと思う。アメリカでこういう治療があることに驚くとともに、日本と同様少数派であることに、残念な気持ちとともに、ある種の納得も感じた。商業主義への対抗はなかなか難しいと。最期のほうでは、アメリカでの教育にも触れており、日本と同様詰め込み教育だというのには驚いた。アメリカは、個性を重視する国と思っていたのに、日本と同様の教育というよりは、訓練を施していたとは驚いた。本書でも心と体の深い関係を考えさせられる。昔、受けたトラウマは、体の不調となって、蓄積されており、根本解決できないと、再発するものなのだと。
Posted by
〈本から〉 生命場 その生命場は全身にくまなく浸透し、さらに皮膚を大きくこえて、全身を包んでいる。それがどんなものかを知りたい人は、からだをとりまく色のついたオーラを想像すればいい。色はその人の状態によって、緑、赤、黄色など、さまざまである。(中略) からだの半分は、われわれがふ...
〈本から〉 生命場 その生命場は全身にくまなく浸透し、さらに皮膚を大きくこえて、全身を包んでいる。それがどんなものかを知りたい人は、からだをとりまく色のついたオーラを想像すればいい。色はその人の状態によって、緑、赤、黄色など、さまざまである。(中略) からだの半分は、われわれがふだん人間として認識している肉体であり、あとの半分は目に見えない「場」なのだ。 直感力にすぐれた人の体は周波数が高い。周波数が高くなればなるほど、霊的な境地が高くなる。 摂氏三十九・五度までの熱なら心配する必要はない。からだはたえず、役割を終えたある種の細胞を焼却しつづけている。それは死滅のプロセスにある細胞で、いずれからだから排出される。そこで母なる自然がふだんより高い熱を発して死んだ細胞を焼却し、排出作用を回復させる。発熱はからだが必要としている正常なはたらきなのだ。 個人の特殊性を無視した、万人に通用するたべかたや完全な食事などというものはありえない。自分の特殊性が判明するまでは、感覚をみがき、からだの反応に注意を払いながら、おいしいと感じるものをたべていればそれでいい。 腹いっぱいたべてもさほど心配しなくていい食品群がある。それは野菜と果物だ。野菜と果物は自然が人間にあたえてくれた最高の贈り物だ。たべておいしく、われわれを元気に、健康にしてくれる栄養素がいっぱいふくまれているだけはなく、生命力おまけもついているのだ。ひと株の植物のなかでは幹や根よりも花は実のほうが周波数が高く、生命力に富んでいる。花や実はその植物の精なのだ。 (中略) 生命力の摂取方法の一つが呼吸だとしたら、もうひとつの方法が野菜や果物の摂取である。
Posted by
オステオパシーという治療法と人間の作りについて描かれている。 治療法については、試してみないと分からないが、誠実な文章から読み取る限り、かなり多くの病気の治療に効くらしい。それも薬なしで。 人間の作りについては、3つの体から成り立つらしい。肉体、霊的な存在、精神的な存在。この辺り...
オステオパシーという治療法と人間の作りについて描かれている。 治療法については、試してみないと分からないが、誠実な文章から読み取る限り、かなり多くの病気の治療に効くらしい。それも薬なしで。 人間の作りについては、3つの体から成り立つらしい。肉体、霊的な存在、精神的な存在。この辺りはスッと理解できなかったのでなんとも言えないが、多くの人が似たようなことを記しているので、恐らく方向性は正しいと思った。
Posted by
読み進めるなかで、心と身体のつながりを想った。 著者は身体を通じて心までも癒す人だ。だからこそ、健康であるためには否定的な『想念パターン』を変える必要があると言えるのだろう。 ●治療者とクライアントとの間に信頼関係が必要であること ●施術の前に治療者はクライアントの話すことに充...
読み進めるなかで、心と身体のつながりを想った。 著者は身体を通じて心までも癒す人だ。だからこそ、健康であるためには否定的な『想念パターン』を変える必要があると言えるのだろう。 ●治療者とクライアントとの間に信頼関係が必要であること ●施術の前に治療者はクライアントの話すことに充分に耳を傾ける必要があること など、その姿勢に同意するところも多い。 ボディワーカーはもちろん、セラピストやカウンセラーも、読んでみて学ぶところが大きい一冊であろう。
Posted by
アンドリュー・ワイル博士の師であり、オステオパシー医の書かれた名著。健康とは何か?がシンプルに書かれていますが、奥深い何度も読み返したい1冊です。セラピストは必読です。
Posted by
吉本ばななの「私はこの本を何回読み返しただろう?何人にすすめただろう?」という言葉に引かれて読む気になった。オステオパシーの名医・フルフォード博士の語り口から感じられる患者や人間への愛、本来の命がもつ力・生命エネルギーへの確かな実感と信頼、地に足のついた医療への態度、そうしたもの...
吉本ばななの「私はこの本を何回読み返しただろう?何人にすすめただろう?」という言葉に引かれて読む気になった。オステオパシーの名医・フルフォード博士の語り口から感じられる患者や人間への愛、本来の命がもつ力・生命エネルギーへの確かな実感と信頼、地に足のついた医療への態度、そうしたものが伝わってきて、なるほど、この感じが吉本ばななにあのように語らしめたのかと思った。 オステオパシーとは、手技を通じて全身の微小関節を調節することによって生体エネルギーの流れに介入し症状の緩和をもたらす骨調整療法であり、アメリカの代表的な代替医療のひとつだが、この生体エネルギーは、明らかに「気」といってよいものである。 1980年代の後半、19世紀の薬剤信仰を嫌っていたアメリカの医師・スティル博士は、 からだに本来そなわっているはずの自然治癒力を最優先する治療法を研究していた。観察を続けるうちに彼は、「どんな病気の患者にもかならず筋骨格系の異常があることに気づき、循環系と神経系のアンバランスが症状を起こしている」と考え始め た。 それを解決するには、手技によって問題の関節を調節することで循環をとりもどすことだとするのがオステオパシーの考え方だ。フルフォード博士は、その正統な後継者のひとりだ。からだには、活発に動くエネルギーの流れが存在し、その流れがブロックされたり圧迫されたりすると、心身が本来もつしなやかさや流動性を失う。 そこから病気の症状が現われる。それゆえ手技によってエネルギーのブロックを解除することが必要になるという。 オステオパシーの治療の一例を挙げよう。からだがだるく大儀で仕事もできずに、死ぬことばかり考えているという50代はじめの男性。何人の医師が検査しても原因が発見できず、膀胱に原因があるのでは、というある医師のすすめで膀胱を切除したが、病状はますます悪くなった。 衰弱し切った患者の診察をしたフルフォード博士は、昔の事故のことを質問した。肋骨あたりに過去の骨折の痕跡が感じられたという。男は驚いて17年前に対向車と衝突した事故のことを語った。その事故のショックがからだの中に残り、生命力がブロックされて、徐々に衰弱していたのだという。10分ほどの手技治療の直後、男は強烈なエネルギーがからだじゅうを駆け巡るのを感じる。数分後には自力で治療台からおき上がり、30分もたたないうちに、男は全身に生命力をみなぎらせて、気持ちよさそうに立ち上がった。 これと同じような事例が数多く紹介され説得力があった。説得力があったという意味は、オステオパシーが手技をつかって特定の関節の調節をすることでエネルギーの流れを取り戻すという点だが、その治療のプロセスとその効果が具体的で、確かな印象を残すのかもしれない。 『免疫革命』は病気の背景にある共通の問題として自律神経系や免疫系の乱れを挙げていたが、実際には、気=生命エネルギーの乱れもまた深く関係しているらしいということ、それが治療の過程で具体的な説得力をもって見えてくるのがの興味深いところだ。 それにしても、病気とその治癒ということを深く追求していくと、現代文明(現代の科学)そのものが持っている根本的な欠陥までもがあらわになってくる。病気と治療ということを通して学ぶべきことはきわめて多い。
Posted by
オステオパシー医の著者が語る体とこころ、魂についての言葉の数々。 真のヒーラーとはこういう人のことなんだろうな。
Posted by
- 1
- 2