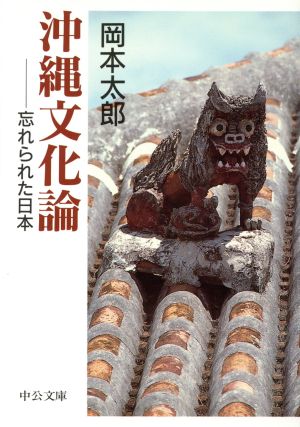沖縄文化論 の商品レビュー
現代アートは好きですし、岡本さんの著作は「今日の芸術」も読んでいたんですが、この本がこれほど魅力的だったとは思いもよりませんでした。 眼を剥いてオカシナ事を口走るオジサン、としか思っていない方は、一読、この文章の水準に驚くのではないでしょうか。 感心したのは、この本、沖縄文化...
現代アートは好きですし、岡本さんの著作は「今日の芸術」も読んでいたんですが、この本がこれほど魅力的だったとは思いもよりませんでした。 眼を剥いてオカシナ事を口走るオジサン、としか思っていない方は、一読、この文章の水準に驚くのではないでしょうか。 感心したのは、この本、沖縄文化の魅惑を語りながら、単なる沖縄論に留まることなく、普遍的な文明論として素晴らしく、芸術一般を語る論考としても優れていることです。 さらに沖縄の風を語る時は、一流の抒情的エッセイとしても読める。 時に確かに納得出来ない論証、賛成しかねる描写もありますが、その考察の鋭さは、文化、文明の深い本質を覗かせ、わずかなそよぎとしか感じられない些細な現象から、魅惑をすくい上げて表現して見せる手並みは抜群です。 芸術家としての感性と、表現者としての力量の両立を感じました。 結局、沖縄という場所が、岡本太郎によほどの驚きと感動を与え、啓発したのでしょう。 沖縄に惹かれている方はモチロン、優れた文明論、芸術論を読みたい方にはオススメの1冊です。 ps 沖縄は「踊る島」だそうで、1章が割かれてますが、以下@ブログ用に改変省略有 「・・そして世界の踊りの喜びがみなここに入り来ているんじゃないか、と極端なことを考える。・・・のびのびと自由にやっているが、洗練されている。民衆自体によほど踊りに対する鋭い姿勢がなければ、とうていこの純粋さと新鮮さを長く保つことは出来ないだろう。凄みである」 個人的には、このエッセンスが安室奈美恵に抽出されている、と考えます。 やっぱり出自からバックグランドがあったのだ。
Posted by
返還前の沖縄を訪ねた岡本太郎による見聞録。沖縄の特に離島の数々に今も残る信仰や芸能にこそ、日本文化の原型が残ると説く。いわく、沖縄が日本に還るのではなく、日本が沖縄に還るべきという指摘が、本土の人間の心にグッと突き刺さる。
Posted by
岡本太郎といえば、エキセントリックな言動の芸術家肌の人かと思っていたので、文章を読んで、こんな理知的に物事を論じることが出来る人なんだということを知って驚いた。 沖縄について、一般的な価値や見方を持って訪問した岡本太郎が、「期待していたものはここでは得られなかった」と、最初に述...
岡本太郎といえば、エキセントリックな言動の芸術家肌の人かと思っていたので、文章を読んで、こんな理知的に物事を論じることが出来る人なんだということを知って驚いた。 沖縄について、一般的な価値や見方を持って訪問した岡本太郎が、「期待していたものはここでは得られなかった」と、最初に述べている率直な感想がスゴい。 これは、よほど自分の審美眼に自信を持って、自分の価値観がはっきりと確立されている人物でなくては言えない言葉だし、そういう彼の視点から見た文化論であるからこそ、語られる意味があると思った。 沖縄本島よりも、そこから離れた離島のほうに岡本太郎は魅力を感じて、離島の記述に重点が置かれているところが面白い。離島になると、鳥葬があったり、人頭税があったり、独自の祭事があったりで、もう、まったく未知の文化で、日本とは完全に別物の文化を持っているように感じる。 もう既に、この本が書かれた時からは50年以上が経過してしまっているし、当時は本土復帰以前だったので、現代の沖縄とはだいぶ違っているのだろうけれど、独特な文化を色濃く残す土地が日本にあるということは、新しい発見だった。 私を最も感動させたものは、意外にも、まったく何の実体も持っていない、といって差支えない、御嶽だった。 つまり神の降る聖所である。この神聖な地域は、礼拝所も建っていなければ、神体も偶像も何もない。森の中のちょっとした、何でもない空地。そこに、うっかりすると見過ごしてしまう粗末な小さい四角の切石が置いてあるだけ。その何にもないということの素晴らしさに私は驚嘆した。(p.40) 昼は夢中で働いているからいいが、夜は淋しい。電気もない。村にトランジスターラジオが二つだけあるそうだ。夜になると村じゅうがそのまわりに集って聞く。だが天気の悪い日はそれも大変だ。若い人たちでも暗くなると早く寝てしまうよりほかはない。青春のエネルギーの苦痛な抑圧だ。(p.57) 人間の声はすばらしい。歌というと、われわれはあまりにも、作られ、みがきあげられた美声になれてしまっている。美声ではない。叫びであり、祈りであり、うめきである。どうしても言わなければならないから言う。叫ばずにはいられない、でなければ生きていかれないから。それが言葉になり、歌になる。ちょうど生きるために動かさなければならない身体の運動と同じように、ぎりぎりの声なのだ。(p.105) この貧困と強制労働の天地に、文化とか芸術が余剰なもの、作品として結晶し、物化するということはできるはずがない。そんな時間、エネルギー、富の余裕はなかった。日夜、ドロのようになって畠を耕し、布を織り続けながら、同時に描き、彫りつけるなんてことは不可能だ。マチエールの抵抗をのりこえて表現する美術とか、「文化生活」なんて思いもよらない。ゆとりはみじんもなかった。それはかつての生活を、いささかホウフツさせる今日の開拓集落の暮らしを直視してもうなずけることである。 だが歌、踊りは別だ。それは今も言ったように生活そのものであり、それなしには生産し、生きることができなかったのだ。ここでは、そのように物ではなく、無形な形でしか表現されなかった。(p.112) それにしても、今日の神社などと称するものはどうだろう。そのほとんどが、やりきれないほど不潔で、愚劣だ。いかつい鳥居、イラカがそびえ、コケオドカシ。安手に身構えた姿はどんなに神聖感から遠いか。とかく人々は、そんなもんなんだと思い込んで見過ごしている。そのものものしさが、どんなに自分の本来の生き方の「きめ」になじまないか、気づかないでいる。(p.169)
Posted by
彼は沖縄に原日本を見たんだと思う 世界で活躍した日本人だからこそ日本というものに対する感性が鋭く、的確に見ぬいたのだろう 沖縄論というより原日本論としての価値を感じる
Posted by
久しぶりに読んでいて、ドキドキした文学だった。 内容も去ることながら、言葉の選び方や文字での表現方法に、鳥肌がたった。 まさに、文字の芸術品。 太郎さんの言葉を借りるならば、『残酷な程に美しすぎる』エッセイだ。
Posted by
岡本太郎が米軍統治下の沖縄を訪れて書いた、名高いエッセイ集。そもそも沖縄にひかれたきっかけが料亭で見た琉球古典舞踊だったというだけあって(124頁)、とくに「踊る島」と題された章はダンス論としても秀逸。日本舞踊ともバレエとも異なる琉球舞踊の特徴を言葉で書き起こした部分は描写の見事...
岡本太郎が米軍統治下の沖縄を訪れて書いた、名高いエッセイ集。そもそも沖縄にひかれたきっかけが料亭で見た琉球古典舞踊だったというだけあって(124頁)、とくに「踊る島」と題された章はダンス論としても秀逸。日本舞踊ともバレエとも異なる琉球舞踊の特徴を言葉で書き起こした部分は描写の見事さにゾクゾクしてしまう。 「情感がもり上り、せまる。そのみちひきのリズムの浮動の中に、私はとけ込んでしまう。目で見ている、観賞している、なんて意識はもうない。一体なのだ。しかし、にもかかわらず、踊り手はまるでこちらを意識していないかのようである。見る者ばかりではない。世界に、身体が踊ってるということの外には何もないという感じなのだ」(127頁) シャーマニズムに関する記述もある。久高島の御嶽(うたき)を訪れて、神聖な儀式の場所が実際は森の中のただの空地でしかないことに衝撃を受けるくだりなど異様なまでの迫力。 「神はこのようになんにもない場所におりて来て、透明な空気の中で人間と向い合うのだ。〔…〕神はシャーマンの超自然的な吸引力によって顕現する。そして一たん儀式がはじまるとこの環境は、なんにもない故にこそ、逆に、最も厳粛に神聖にひきしまる」(168-9頁)。
Posted by
沖縄×岡本太郎・・・面白くないはずはない! その導入から筆者の美意識に粛然とした。 著者は文字をもてなかった歴史の上に成り立つ歌・踊りといった無形のものや御嶽と呼ばれる神の聖所に心を奪われる。 そして沖縄の人の自然と生活感情を同質させ、こだわらないが投げやりでない生き方に素っ裸の...
沖縄×岡本太郎・・・面白くないはずはない! その導入から筆者の美意識に粛然とした。 著者は文字をもてなかった歴史の上に成り立つ歌・踊りといった無形のものや御嶽と呼ばれる神の聖所に心を奪われる。 そして沖縄の人の自然と生活感情を同質させ、こだわらないが投げやりでない生き方に素っ裸の原始日本を見る。 1959年というアメリカ統治下のレポートのため、現在の様相とは大分異なるはずだ。 しかし、著者が直観した深遠な魅力は、50年を経ても憧憬の的として私を惹きつける。
Posted by
身体、というもの、根源にある力みたいなものをかんじられる場所なのかも。 女性が宗教的なパワーを持った存在として優位に立つのも興味深い。
Posted by
芸術を創りだすとか、文化が何ぞやとか...、それを語るとか... そんな事を全く無視して存在するもの...って事なのか??? あの岡本太郎が『ビビーーット』来てしまった素の沖縄 観光の沖縄ではなくて、裏っかわの沖縄を覗きに.... 行けるものなら..行きたいと思ってしまう。
Posted by
沖縄、それは岡本太郎にとって日本が残ると感じた場所だった。何もない、そう何もないのだ。彼にとって、沖縄を感じさせるものは、首里城やら焼き物ではなかった。石垣であり、舟であった。何か想いなりを込めて作った芸術ではなく、長い時間をかけて、生活が、自然が、意味を削っていった、純粋なる...
沖縄、それは岡本太郎にとって日本が残ると感じた場所だった。何もない、そう何もないのだ。彼にとって、沖縄を感じさせるものは、首里城やら焼き物ではなかった。石垣であり、舟であった。何か想いなりを込めて作った芸術ではなく、長い時間をかけて、生活が、自然が、意味を削っていった、純粋なる記号が彼を捉えたのだ。単純であること、自然であること。それが彼らから感じた事だとまとめられるかもしれない。 ロラン・バルトの「表徴の帝国」に通じるものを感じた。再読する必要性が絶対にある本だ。
Posted by