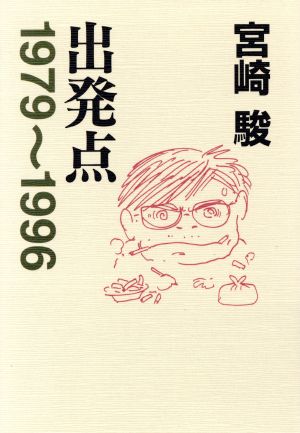出発点 の商品レビュー
140冊目『出発点〔1979〜1996〕』(宮崎駿 著、1996年7月、スタジオジブリ) 宮崎駿が1979年から1996年の間に発表したエッセイや作品解説、対談などをトピックごとに纏めた500ページを超える大作。 長編監督デビュー作『カリオストロ』が1979年、映画興行史を塗り替...
140冊目『出発点〔1979〜1996〕』(宮崎駿 著、1996年7月、スタジオジブリ) 宮崎駿が1979年から1996年の間に発表したエッセイや作品解説、対談などをトピックごとに纏めた500ページを超える大作。 長編監督デビュー作『カリオストロ』が1979年、映画興行史を塗り替えた『もののけ姫』が1997年の公開であり、奇しくも宮崎駿の作家人生において、最も激動の時代といえる18年間が記録されている。 〈子どもにとって、怖いとか、不気味というのは、可愛いとか、面白いとかと交ざっているんです〉
Posted by
図書館で借りた。 厚くて読みきれずに返却期限がきて泣く泣く返却。 宮崎駿のインタビューや対談、書いたものなどがまとめてある本。 タイトルにある通り1996年までなので、「もののけ姫」の公開前までになる。 私は「もののけ姫」以前までくらいの宮崎駿作品が割と好きなので、ちょうどよかっ...
図書館で借りた。 厚くて読みきれずに返却期限がきて泣く泣く返却。 宮崎駿のインタビューや対談、書いたものなどがまとめてある本。 タイトルにある通り1996年までなので、「もののけ姫」の公開前までになる。 私は「もののけ姫」以前までくらいの宮崎駿作品が割と好きなので、ちょうどよかった。 「カリオストロの城」と「ラピュタ」が一番好きで、「ナウシカ」も好き(漫画版のナウシカの方がもっと好き)という感じなので。 裏方ばなしが色々書いてあるので楽しく読んだ。 またしばらくしたら借りてきて続きを読もうと思う。
Posted by
その作品の殆どを観た「巨匠」宮崎駿の実像に迫る580ページの大書。図書館返却期限に急かされ、僅か一日半で読破した。 いやー、オモシロかった! 彼はクリエイターであると同時に、優れた評論家、批評家、思想家でもあるのだな。 イマドキの映画やアニメの作り手には先ずいない、稀有な才能であ...
その作品の殆どを観た「巨匠」宮崎駿の実像に迫る580ページの大書。図書館返却期限に急かされ、僅か一日半で読破した。 いやー、オモシロかった! 彼はクリエイターであると同時に、優れた評論家、批評家、思想家でもあるのだな。 イマドキの映画やアニメの作り手には先ずいない、稀有な才能であることをあらためて再認識させられた好著。
Posted by
宮﨑駿の企画書・演出覚書・エッセイ・公演・対談等90本を収録。 テーマごとに分かれていますが、時間軸も元々バラバラですので、気になるところから読み進めても大丈夫です。 漫画版「風の谷のナウシカ」が好きで、なぜこんな漫画が描けるのだろうと、関連の本をいくつか読んでみましたが、これ...
宮﨑駿の企画書・演出覚書・エッセイ・公演・対談等90本を収録。 テーマごとに分かれていますが、時間軸も元々バラバラですので、気になるところから読み進めても大丈夫です。 漫画版「風の谷のナウシカ」が好きで、なぜこんな漫画が描けるのだろうと、関連の本をいくつか読んでみましたが、これ一冊で良かったくらい内容は充実しています。 しかしながら、これを読んでナウシカが理解できるかと言うと決してそうではありません。 誰も理解できないから魅力があるのだと思いました。 宮﨑駿という人は、よく言われるように矛盾を抱えたまま物を書く人ですし、自分の無意識から掬い上げてイメージを膨らます人なので、本人にもわかっていないことが多いからだと思います。 とりあえず描いてみて、それを常に疑いつつあとでその意味に気付くということを繰り返しています。 本人も言っていますが、どうしても「こうなっちゃう」のです。 それは作者の自然や社会や戦争に対する膨大な知識も、幼少期に形成された感覚も、全てごちゃ混ぜになって一つの塊として生み出そうとしているからではないかと思いました。 それだけの膨大なアイデアや思想を一本のストーリーに練り上げる創造力と画力は想像を絶します。 連載といっても何度も休載していますし、1ページでもいいから続きを描いてくれという雑誌側の配慮があったことも奇跡的に良かったのだと思います。 風の谷のナウシカは読む人によって、SFともとれますし、戦記物とも、環境問題とも、大河ドラマとも、旅行記とも、親子の話ともとることができます。 そのせいもあってか、まとまりがないとも思われる宮﨑作品ですが、その根本には、残酷な現実世界の中で逞しく生きてほしいという願いがあります。 その願いが、ご都合主義のラストにはせず、問題は簡単には解決しないけど、その中で助け合って良いも悪いも共有して生きていこうとする主人公たちに表れているのだと思います。 しかしながら宮﨑駿のアニメ論が展開される一方で、この本の内容は宮﨑駿が自身の制作について語ることが殆どを占めていますので、側からみた宮﨑駿は、これまた全く違います。 このことについては、押井守の「誰も語らなかったジブリを語ろう」を読むとまた違った視点から宮崎駿の制作をみることができるのでお勧めします。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
90本の記事。 ・アニメーションを作るということ ・しごとの周辺 ・人 ・本 ・好きなこと ・対談 ・企画書・演出覚書 ・作品 という章立て、その中で編年体。 目次が全然目次になっていないので、目次に発表年を書き込みして、それぞれの記事がどの作品の前後なのか照らし合わせて、ようやく各記事が腑に落ちる。 というわけで続編「折り返し点」のような完全編年体のほうが好み。 「ジブリの教科書」シリーズで引用されたもの多数。 記事としては「コナン」後から始まるが、来歴を語るものもあるので、アニメーター時代から監督へ。 作家性としては「深いニヒリズム」が熟成される過程そのもの。 「もののけ姫」準備中まで。 矛盾の塊、多面体、情熱の火柱。 単純な感想としては、親の目線を含む、子供の視線、その混合が、いいんだなぁ。
Posted by
あらゆる媒体で宮崎駿が発言したり書いたりしたものを一挙に読める一冊。1992年6月19日仙台市の八幡小学校6年3組で講演(?)した際の「こんな映画を作りたい」など、こんなものまで!と思える貴重な記録を楽しめる。 手塚治虫が亡くなった際の文章では散々ディスった最後に”天皇崩御のとき...
あらゆる媒体で宮崎駿が発言したり書いたりしたものを一挙に読める一冊。1992年6月19日仙台市の八幡小学校6年3組で講演(?)した際の「こんな映画を作りたい」など、こんなものまで!と思える貴重な記録を楽しめる。 手塚治虫が亡くなった際の文章では散々ディスった最後に”天皇崩御のときより昭和という時代が終わったんだと感じました”とか、押井守との対談で散々ダメ出ししたりとハラハラしながらも、映画作品からだけでは読み取れない宮崎作品の一端を垣間見れたような気がします。
Posted by
宮崎駿の考え方。 戦後アニメで鉄腕アトムなど子どもが活躍するものが流行った。それは大人が信用できなくなったから。それがいつの間にか大人のための先行投資の時期になった。 映画は最後まで見るので評論が成り立つ。マンガは面白くないものは読み飛ばす。 少女漫画は見たくないものは描かない。...
宮崎駿の考え方。 戦後アニメで鉄腕アトムなど子どもが活躍するものが流行った。それは大人が信用できなくなったから。それがいつの間にか大人のための先行投資の時期になった。 映画は最後まで見るので評論が成り立つ。マンガは面白くないものは読み飛ばす。 少女漫画は見たくないものは描かない。文字と空白の表現。 クリスマスツリーは星が良いなと思うかもしれないが、星だけ作ってはだめで、幹がないとツリーにはならない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
宮崎駿監督の対談集。 読み切ることにとても時間が掛かってしまった。エッセイならまだしも、こうして受け手として読まれるために話されたものではないので、とても読みにくい。 そして宮崎駿監督の人となりがなんとなく見えてくるような会話が多かった。監督の歴史、生活史、目指しているものと、描きたいことを代表作ナウシカからもののけ姫あたりまで網羅されている。ジブリ好きにはたまらない内容。 企画書としての映画の概要もとても興味深く読めた。初めはきっと文章で書かれた簡単なあらすじ、メモ帳に残しておいた一節、あるいはイメージボードと呼ばれていた落書きのひとつが、ジブリの世界観を作りたらしめる細微となって積み重なっていくものなのかもしれない。 それにしても紅の豚の「中年男性が夢見る映画」といわれていたのが面白かった。もちろん紅の豚のポルコは誰から見てもかっこいいのかもしれないが、確かに言われてみれば魔女の宅急便やトトロのように、子供対象ではないように感じていたので、合点が入った。少し難しいようでいて、とても単純な夢見ている部分を描かれているからこそ、ああして映画として魅力的なのかもしれない。 ジブリファンの人からすれば宮崎駿監督の気難しさや天才肌な部分は有名なことなのかもしれないが、この本を読み、あるいはあとがきの高畑監督の言葉を添えられると、さらにその輪郭が明瞭になっていく。その姿勢からは、ジブリというスタジオで”漫画映画”から人々が夢見る形を商業として成り立たせなければならない、そんな矜持を垣間見ることができる。
Posted by
『墨攻』アニメ化の際はスタッフに押井守御大が呼ばれたさうである。あんだけ才能のある人が来るとかえって制作が頓挫するのは世界の定説の筈である。 『栽培植物となんちゃら』に関して、見つけた時を衒ふまいとか書いてあって、へーさうなんだと思ってゐたが、スイスでへこんだ後で帰国後その本を...
『墨攻』アニメ化の際はスタッフに押井守御大が呼ばれたさうである。あんだけ才能のある人が来るとかえって制作が頓挫するのは世界の定説の筈である。 『栽培植物となんちゃら』に関して、見つけた時を衒ふまいとか書いてあって、へーさうなんだと思ってゐたが、スイスでへこんだ後で帰国後その本を発見、は、中尾先生が説く「アルプス以北の農耕を日本もやるべき」を彷彿とさせた。ただ宮崎さんは一貫して嘗ての田圃とかを書いてをり、然るべきそれを書いてゐない。 『ロールフ』ジブリのアニメで見たいなぁ。
Posted by
途中までは頑張って読んだけど、半分過ぎたインタビューあたりから辛くなってきた… いつか全部読みたい。
Posted by