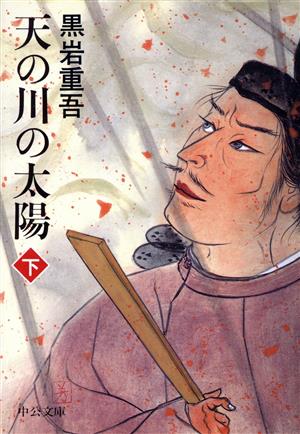天の川の太陽 改版(下) の商品レビュー
兄、中大兄皇子(天智天皇)の皇太弟として次期天皇を期するも、天皇の子の大友皇子が新天皇に指名され、出家して吉野に隠遁する大海人皇子。 敢えて忍従しつつも東国の反近江朝廷派の力を集積し、機が熟したところで反撃の狼煙を上げる。 672年に起きた大海人皇子と大友皇子による「壬申の乱」...
兄、中大兄皇子(天智天皇)の皇太弟として次期天皇を期するも、天皇の子の大友皇子が新天皇に指名され、出家して吉野に隠遁する大海人皇子。 敢えて忍従しつつも東国の反近江朝廷派の力を集積し、機が熟したところで反撃の狼煙を上げる。 672年に起きた大海人皇子と大友皇子による「壬申の乱」をテーマにした壮大なドラマ。高校生の頃に年号と名前だけを丸暗記しただけのことを50年たった今、あらためて事の真相を知る素晴らしい時間だった。 数年前、関ケ原と垂井町を歩き回ったときに、なぜここに壬申の乱の史跡があるのかと不思議に思ったがその理由がよく分かった。その時の土地勘があったので内容も楽しく読めた。 ただ黒岩さん、丁寧に描きすぎて少々長すぎる。その分ゆっくり時間が過ぎるので人名や経過がとても分かりやすかったのはよかったけど。
Posted by
中臣鎌足そして満を持して兄の天智天皇が死に、大友皇子が弘文天皇に即位するも、母親の出自がしもじもなので別に悪いことをしてないのに人望がなく、他方、吉野に隠遁した大海人皇子は父母とも天皇という高貴な生まれなので劉備玄徳ばりにやたらと人望があり、かき集めた東国の兵士も活気満ち溢れ、何...
中臣鎌足そして満を持して兄の天智天皇が死に、大友皇子が弘文天皇に即位するも、母親の出自がしもじもなので別に悪いことをしてないのに人望がなく、他方、吉野に隠遁した大海人皇子は父母とも天皇という高貴な生まれなので劉備玄徳ばりにやたらと人望があり、かき集めた東国の兵士も活気満ち溢れ、何百ページも費やして壬申の乱で勝利を収め、他方、人気のない弘文天皇は次々と味方が離反しかきあつめた西国の兵士に活気ゼロで負けて当然という、何か大友皇子にうらみでもあるかのような書きぶり。近畿の地名とやたら人物名がでてくるので読み終わるのに難儀した。
Posted by
上巻に引き続き、大海人皇子は石橋を叩いて叩きまくりながら、対中央朝廷の準備をすすめる。そして、待ちに待った兄の天智天皇の死。大海人皇子は味方にした地方豪族たちを率い、三万の軍勢で近江宮を目指す。 著者は限られた資料や当時の戦場の地形、人々の体力や走力などを分析し、壬申の乱の局地...
上巻に引き続き、大海人皇子は石橋を叩いて叩きまくりながら、対中央朝廷の準備をすすめる。そして、待ちに待った兄の天智天皇の死。大海人皇子は味方にした地方豪族たちを率い、三万の軍勢で近江宮を目指す。 著者は限られた資料や当時の戦場の地形、人々の体力や走力などを分析し、壬申の乱の局地戦を詳細に描き出す。下巻のほとんどがこの戦乱描写なのだが、あまりに詳細すぎて読むのがつらかった。あまり知られていない将軍や舎人に比べて、額田王や大友皇子の登場が少なく、人間ドラマそっちのけの下巻は、小説というより歴史書に近い。 と、そんな不満は置いといて、本作品を読んでわかった大海人皇子が圧勝した理由は2つ。一つは緊迫する海外情勢を知る大友皇子側が新羅や唐の侵入を警戒していたこと。仮想敵は海外であり、東国に下った大海人皇子を警戒する余裕がなかった。もう一つは、大海人皇子が天皇は自分であり、今回の戦いの目的を天皇への反逆者である大友皇子の征伐としたこと。だから、豪族たちは天皇へ忠誠を尽くすために大海人皇子に従った。 そんな勝因に加え、才能、魅力に優れた人間性を備えた大海人皇子は勝つべくして勝った。
Posted by
いよいよ大海人は吉野に逃れ、美濃・伊勢・尾張の豪族や飛鳥や河内の官人を動員し、来るべき日に向けて着々と準備を進めます。美濃での動員が近江側に知られ、大海人は吉野を脱出し、叛乱の烽火をあげます。不破と飛鳥で先端が切られ、ついに大海人は勝利し、大友の首級をあげます。 勝利によって皆が...
いよいよ大海人は吉野に逃れ、美濃・伊勢・尾張の豪族や飛鳥や河内の官人を動員し、来るべき日に向けて着々と準備を進めます。美濃での動員が近江側に知られ、大海人は吉野を脱出し、叛乱の烽火をあげます。不破と飛鳥で先端が切られ、ついに大海人は勝利し、大友の首級をあげます。 勝利によって皆が喜びの中、大海人の舎人達と大海人は、今までのお互いの関係が変わったことを感じます。もはやともにの山を駆ける間柄ではなくなってしまったのです。 確実に戦いの準備を進めていく大海人ですが、その心は大きく揺れます。勝利への確信を得たかと思えば、近江側に恐れも抱きます。その都度、舎人や讃良に励まされて心を奮い立たせます。近江側からの圧迫、旗色をはっきりさせない東国の官人、味方でもその目的は様々です。 まさに、手に汗握る、胃がきりきりしそうな物語が展開されます。
Posted by
まず、壬申の乱の記紀の少しの記述からここまでの物語に仕上げるその想像力がすばらしい。小説とはそういうものだといわれたらそれまでであるが、にしても天智天皇と天武天皇の関係を時代背景(と思われる状況)を丁寧に辿りながら、額田王や讃良姫等の恋物語も混ぜながら単なる歴史書に留まらない人間...
まず、壬申の乱の記紀の少しの記述からここまでの物語に仕上げるその想像力がすばらしい。小説とはそういうものだといわれたらそれまでであるが、にしても天智天皇と天武天皇の関係を時代背景(と思われる状況)を丁寧に辿りながら、額田王や讃良姫等の恋物語も混ぜながら単なる歴史書に留まらない人間関係の物語として昇華させている。 壬申の乱はそれほど印象深く日本史の教科書で取り扱われているわけではないが、本書を読んで大和-飛鳥-奈良時代の歴史への関心が深まった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
下巻では、大友皇子に天皇位を奪われ、出家して吉野に隠遁していた大海人皇子が綿密すぎるほどに計画し、挙兵するまでの様子を描く。宮滝に落ち延びてからも決して態度を変えず大海人に寄り添い続ける勝気な妻、鸕野讃良との絆の深さも印象深い。 身分に隔たりのある舎人たちと心を通わせるなど、懐の大きな大海人に心を寄せるものは東国にも王族にも朝廷内にも多く、彼らは近江朝廷に愛想を尽かしてしばしば大海人を慕い、挙兵を促す。しかし大海人は舎人たちにさえギリギリまで本心をひた隠しに隠して、水面下で準備を推し進めていく。 決戦の日に備え、部下たちに土地勘を養わせたり、より強力な武器を製造させたり、まだ皇太弟として権威を失っていなかた頃からの、用意周到さは驚嘆に値する。 ただ、本のボリュームに対して「決して気づかれるな」という、同じ場面の繰り返しがあまりにも多くて少し飽きてくる。解説や自説の展開も多い。小説としてのテンポや流れは決して良いとは言えない。 しかしそれぞれの人物の個性や心情の移り変わりは鮮やかに魅力的に描き出されていて、強い印象を残してくれた。
Posted by
この小説は天武天皇(大海人皇子)と、天智天皇の皇子(大友皇子)の戦い「壬申の乱」について描かれたものです。 色々な立場の各登場人物の心の移り変わりの様子が丁寧に書かれており、また、身分(血統)や階級が絶対的だった時代ならではのモノの見方や考え方に触れることによって、古代をいつも...
この小説は天武天皇(大海人皇子)と、天智天皇の皇子(大友皇子)の戦い「壬申の乱」について描かれたものです。 色々な立場の各登場人物の心の移り変わりの様子が丁寧に書かれており、また、身分(血統)や階級が絶対的だった時代ならではのモノの見方や考え方に触れることによって、古代をいつもとは違う視点で味わうことができました。 いつもとは違う視点、といえば大海人皇子に仕える舎人たちがかっこよくて、少女マンガのような気分で読めたのも楽しかったです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
鉄剣を磨き、馬を養って時に耐える大海人皇子はついに立った。東国から怒涛のような大軍が原野を埋めて近江の都に迫り、各地で朝廷軍との戦いがはじまる。激動の大乱のなかの息詰まる人間ドラマの数々。歴史学をふまえて錯綜する時代の動きをダイナミックにとらえた長篇。 1997年7月27日購入
Posted by
この作品は黒岩重吾氏が初めて古代史に取り組んだ歴史長篇である。 昭和51年(1976)より連載され、昭和54年(1979)に刊行された。 作品が発表される数年前に奈良県の明日香村で高松塚から壁画が発見され タブー視され続けていた天皇家及び古代への感心が高まっていた時期であった。 ...
この作品は黒岩重吾氏が初めて古代史に取り組んだ歴史長篇である。 昭和51年(1976)より連載され、昭和54年(1979)に刊行された。 作品が発表される数年前に奈良県の明日香村で高松塚から壁画が発見され タブー視され続けていた天皇家及び古代への感心が高まっていた時期であった。 一部の人を除き古代への感心が今一つなのは当時のことが謎に包まれて、 未だに研究者達の間でも論争が続いてはっきりしないことや、 その当時の人々の姿が思い浮かばないからであると思われる。 実際古代史好きのあたしにも、当時はどんな服装だったのか、 どんな住居でどのように暮らしていたのか、想像でしかないので こういった古代史作品を読んで、文字と雰囲気でしか分からない。 しかし黒岩氏の作品のどこがすごいのかと言うと、 登場する人物一人一人が実に活き活きとしていて読んでいる時も 映像として想像できるところだと思う。 戦が行われた場所も、行った事も見た事もないあたしでも その文字を追うだけで映画館で見るような迫力ある映像が頭に浮かぶのだ。 登場人物も顔の細部までは想像出来ないけれど その時々にどんな表情をしていたかまで思い浮かべることが出来る。 一人一人がとても魅力的なので、読んでいて目頭が熱くなる。
Posted by
- 1