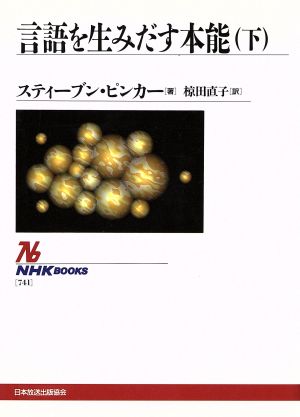言語を生みだす本能(下) の商品レビュー
言語(話し言葉)に関しての系統的領域、発生論的領域、脳科学的領域、進化論的領域に加え、言語の流動性に関して考察した書籍。
Posted by
生得と学習の二元論ではなく、基本設計としての普遍文法を原理として生後の環境に応じた言語を獲得していくという考えに概ね納得できた。第11章「ビッグバン」では、これまでの人類の進化プロセスの中でどのように「言語」を司る機能が生じたのかについて、いわゆる一つの幹ではなく枝葉に別れて生物...
生得と学習の二元論ではなく、基本設計としての普遍文法を原理として生後の環境に応じた言語を獲得していくという考えに概ね納得できた。第11章「ビッグバン」では、これまでの人類の進化プロセスの中でどのように「言語」を司る機能が生じたのかについて、いわゆる一つの幹ではなく枝葉に別れて生物が進化してきたと解釈すれば、たとえばチンパンジーなどが文法的な言語処理ができないことが決して不思議ではないという話があった。進化論の理解も改まったが、言語能力の萌芽が他の種にもあるはずだという考えがいかに素人的なものか痛感させられた。
Posted by
学生時代のドリル自己採点。 不正解の問題をそのままにしていた。 今一度取組もうとする姿勢が浅かった。何がわからないか見つけ出すことに意味があったのに。 下巻。全く歯が立ちませんでしたねぇ。上巻はスイスイやったのに。もう一回、読んで分かる日がくるかな。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1995年刊行。チンパンジーの言語獲得に関する議論は「カンジ」(手話ベース)のみで、「アイ」「アユム」には全く触れられない。言語面でヒトとチンパンジーとの間に隔絶した差があることは否定しない(確かに、萌芽的なものでしかない)が、舌足らずの感。また、言語指南役への批判も、それが本論との関係でいかなる意味を持つのかいまいち不明。そもそも言語獲得生来説でも、後天的な言語環境を無視するわけではなく、批判の目的が判然としないゆえ。心の点も、言語と異なり、脳地図では全く表せず、論の検証が難しいとも思えたところ。
Posted by
ジョーク交じりの文体がどうしても苦手でとても時間がかかりました。 内容的にはけっこう面白いんですが,体系だった知識を得ようとすると,急に読むのが大変になります。逆に空き時間でファッショナブルに言語学に触れるには良い本だと思いました。
Posted by
下巻で中心になるのは言語と進化論の関係について。言語が複数存在するのは生物の種と同様、変化・継承・孤立といった事柄が長い時をかけて進行したからという主張は、今まさに様々な種族と言語が共に失われつつあるという現実が証明している。また赤ん坊は出産直後は世界中のあらゆる音素音節を聞き分...
下巻で中心になるのは言語と進化論の関係について。言語が複数存在するのは生物の種と同様、変化・継承・孤立といった事柄が長い時をかけて進行したからという主張は、今まさに様々な種族と言語が共に失われつつあるという現実が証明している。また赤ん坊は出産直後は世界中のあらゆる音素音節を聞き分ける能力を持って生まれてくるというのは目から鱗であり、やがて母語の音声しか聞き取れなくなると同時に単語を理解し始め、一人歩きを始める頃に文法を獲得していくという流れには、やはり言語が本能的な部分と関係しているのだと納得させられる。
Posted by
言語は後天的に身につけるものである、とは言い切れないというのが本書の主張するところ。いままで何の疑いもなく、言語は後天的なものだと思っていたのですが、本書を読んで、人間の本能レベルのところで言語を生み出す仕組みがあるという考え方にも一理あると感じました。心理学、言語学からコンピュ...
言語は後天的に身につけるものである、とは言い切れないというのが本書の主張するところ。いままで何の疑いもなく、言語は後天的なものだと思っていたのですが、本書を読んで、人間の本能レベルのところで言語を生み出す仕組みがあるという考え方にも一理あると感じました。心理学、言語学からコンピュータ科学にもちょっと触れていたりします。しかし、1990年代半ばの本のため、若干内容が古いかもしれません。言語学に絡んだ話としては、原著が英語であることから当然なのですが、英語文法を題材にしたものが多いです。ちょっとこれが読むのがつらかった。この本は読んでよかったと思える本です。この本を読んだ上で、「語りえぬものには沈黙しなければならない」という某哲学者のフレーズを、もう一度咀嚼したくなりました。※上下巻とも同じレビューです。
Posted by
言語を生み出す本能(下) 上巻は、ある程度面白いながらも、言語学の細かい内容についていけず、消化不良のままな感じだったが、下巻はずいぶん読みやすかった。 こどもがどのように言語を習得していくのか、動物で言語を取得したものが無いこととその理由、人間がどのように言語を習得したのかとい...
言語を生み出す本能(下) 上巻は、ある程度面白いながらも、言語学の細かい内容についていけず、消化不良のままな感じだったが、下巻はずいぶん読みやすかった。 こどもがどのように言語を習得していくのか、動物で言語を取得したものが無いこととその理由、人間がどのように言語を習得したのかという仮説の検証など、そして最後に、自称評論家に対する批判。軽快な文体で、バサバサと斬っていくのが小気味良い。 ただ、主張よりも他者の批判の方が先立ってしまう感じがして、結局結論が何なのかというところが明確ではないようにも感じた。 最後の、自称評論家に対する批判は、どこの国でも一緒だなあ。スラングや若者言葉はすべて心的文法に反していないという言語学者による批判はとても説得力がある。実際、これまでの歴史でも言葉はどんどん使ううちに進化してきたものである。だけど、いつの時代でも、新しい言葉に対する批判はあって、変える力と変えない力が引っ張り合って最終的な言葉の進化が起こるように思う。 多くの人がレビューで書いているように、この本はたぶん原書で読むべきなのだろう。日本語で読んでも意味のよくわからない部分もたくさんあった。きっと翻訳者は苦労したろうと思う。そして、原書で読んだとしても、英語スピーカーではないために、直感的にはわからないところもたくさんあって、おもしろさの半分も理解できていないだろう。日本語の話だったらもっと面白いだろうなと思う。 それでも、チョムスキーの名前すら知らなかったわたしにとって、こういう考え方があることはとても勉強になったし、面白かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] すべての子どもは、文法の基本原理を生まれつき持ちあわせて誕生するが、3歳までにどのように天才的に言葉を習得するのか。 脳内のどこかに文法の遺伝子を見出せるのか。 人類史上、言語はなぜ、いかに発生、進化したのか。 スラングや方言などは、言語の堕落を招くのか。 世界をリードする少壮の心理言語学者が、言語本能論に基づき、言葉についてのさまざまな疑問に明快に答える。 [ 目次 ] バベルの塔―言語の系図 しゃべりながら生まれた赤ちゃん、天国を語る―母語を習得するプロセス 言語器官と文法遺伝子―脳のなかにさぐる ビッグバン―言語本能の進化 言語指南役たち―規範的ルールの誤り 心の構図 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
- 1