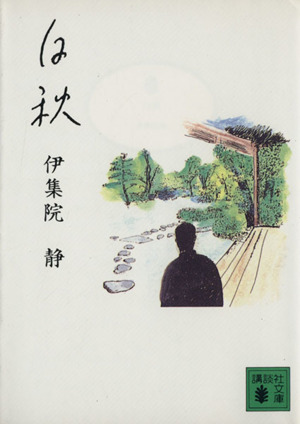白秋 の商品レビュー
著者の作品で最も好き…
著者の作品で最も好きな作品。水彩画のような透き通った、儚く、切ないお話。とても綺麗なお話です。
文庫OFF
幼い頃より病身の真也…
幼い頃より病身の真也と二人の女性の、恋と、もつれを、美しくもせつない文体でつづる名作。伊集院ワールドと呼ばれる繊細で表現力豊かな感性は、そのまま優れた芸術品と言っていいと思う。
文庫OFF
一文一文が美しい!地元なので、勝手ながら第2の故郷のように感じている鎌倉の情景が鮮明に浮かんできた。海が近くにある暮らしはやはりいいですな。
Posted by
鎌倉を舞台にした、美しい小説だった。 27歳になった真也は子どもの頃からの心臓病で、病院生活を繰り返し、鴨川の病院から連れて来た志津という看護婦と鎌倉の家で静養している。 治る見込みのない生活の中で、志津は、月見廊下に花を活けて真也に見せようと思いつく。 数軒先に高名な生...
鎌倉を舞台にした、美しい小説だった。 27歳になった真也は子どもの頃からの心臓病で、病院生活を繰り返し、鴨川の病院から連れて来た志津という看護婦と鎌倉の家で静養している。 治る見込みのない生活の中で、志津は、月見廊下に花を活けて真也に見せようと思いつく。 数軒先に高名な生花の師匠が居て、そこから文枝と言う娘が花を活けに通ってくることになった。 活けられた花を見て、信也はぼんやり幻のように見た女性が現れて花を活けているように思う。 野の花をあしらった生花の飾り気のない美しさ、文枝が身に纏った雰囲気まで、彼が待っていた女性だった。 信也はアメリカの移植手術が成功したというニュースで、文枝との淡い未来を夢みる、しかし患者が7ヵ月後になくなったということを知る、常に背後から死の足音を聴き続けたような毎日が、また続く、かすかな希望が崩れていく、彼の絶望感が痛々しい。 恋に落ちた二人に気がついて志津の嫉妬は狂気を帯びてくる。外に風に当たるだけでも体調を壊して寝込む信也は、文枝に会うために志津の目を盗んで浜に月を見に出る。出入りの道具屋の機転で、二人は出会い、結ばれる。 と言う少し現代の恋愛小説には珍しい純愛が、静かな美しい文章で書かれている。鎌倉に咲く季節の花、特に野山の何気ない花が、陶器の一輪挿しや竹かごに活けられる、月見の夕べはすすきに桔梗、時には白萩や吾亦紅、山から摘んできた杜鵑、ひよどり草などが信也が住んでいる書斎や茶室、築山を配した庭などにしっとりと馴染んでいる。 慌しい現代の恋愛に比べて、病身の青年と和服の似合う女性という組み合わせに、どことなく距離感があるにしても、この品のいい作品を何かの折に心静かに読みなおしてみたい。 道尾さんの「月と蟹」を、読み込まれて書かれている上に、子どもたちの住んでいる鎌倉の、風景や海の香が漂う解説を読んで、伊集院さんのこの「白秋」を読んでみたくなった。 一度は読んでおかないといけないと思ながら漏れているものがまだまだ多い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
とにかく、文章が美しい! ひさびさに、ゆっくり読み進めたい本でした。 日本語の響きって、こんなにきれいだと再確認。 流行りの本には、こんな素敵な文章は無い。 男主体の、古い価値観の話だけど、不快ではない。 真也さんと文枝さん、幸せに暮らしてほしかったな…
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
鎌倉の四季折々の情景描写が素晴らしかった。 花を生けたくなる。 志津さんが2人の恋を素直に応援していたら、真也はもっと長く文枝さんとの時間を取れただろうに、と思うと切ない。 最後に書いてないので、錯乱した後の志津さんはどうなったのかが気になる。 真也亡き後は、志津さんも誰かと幸せになってほしい。
Posted by
はじめて読んだ伊集院静さんの小説。 冒頭の七草粥をつくる台所の場面の描写がよくて その感慨のままに読み進めた。 だけど展開が、始めのうちは人間模様がきれいすぎ、 後半は看護婦志津がすっかり悪者、除け者扱いに。 これではあんまりだと思った。 どうしても男性が恋の相手女性を描写すると...
はじめて読んだ伊集院静さんの小説。 冒頭の七草粥をつくる台所の場面の描写がよくて その感慨のままに読み進めた。 だけど展開が、始めのうちは人間模様がきれいすぎ、 後半は看護婦志津がすっかり悪者、除け者扱いに。 これではあんまりだと思った。 どうしても男性が恋の相手女性を描写すると、汚点の ない、純粋無垢そのものにしたがるんだなぁ…とまた思った。
Posted by
ロマンティックだなぁ。 夢見る中学生的憧れのような小説だった。 ちょっと、キレイ過ぎるくらいだ。 お花の描写が美しかった。
Posted by
久しぶりに文学しました。 こんな本何年ぶりに読んだだろうと言う感じです。 まさに文学と言う感じの書き出しで始まり、和服の落ち着いた女性、日本家屋、古都、茶道、華道、病弱な青年そして愛憎。 こんな要素が含まれる作品を文学と呼ぶのだろうと、何となく思ってしまう、やっぱり文学作品...
久しぶりに文学しました。 こんな本何年ぶりに読んだだろうと言う感じです。 まさに文学と言う感じの書き出しで始まり、和服の落ち着いた女性、日本家屋、古都、茶道、華道、病弱な青年そして愛憎。 こんな要素が含まれる作品を文学と呼ぶのだろうと、何となく思ってしまう、やっぱり文学作品でした。 筋としては、病弱な青年とそれを看護する中年ではあるものの、未婚の看護人の二人の主従関係に基づく長い闘病生活に始まり、そこに出入りするようになった、若い和服の似合う活け花のお弟子さん。 青年と活け花を池に来る女性が互いに引かれていくが、それに嫉妬する看護人。 二人を応援する人が増えるごとに、看護人の愛憎が増長し、二人を別れれさせようとするが、最後は二人の思いが通じ結ばれる。 しかし病弱な青年は願いが成就した直後に他界し、年若い女性が青年の子を身ごもると言うなんともどこかで見たような結末になるのだが、落ち着いた文体や、四季を感じさせる花々の描写が、都市生活を描く小説とは一線を画す。 たまにはこんな読書もいいかもしれない。
Posted by
伊集院氏の描く男女の心模様は、繊細で切ない気持ちにさせますね。「花も人も何も変わりません。咲こうとする生命力、咲いている力は、人間が生きることと同じです。その生命が美しく、その力がゆたかであるのです。」(P94)。「生き残ったのは、運が良かったのではなく、そこが私の死ぬ場所ではな...
伊集院氏の描く男女の心模様は、繊細で切ない気持ちにさせますね。「花も人も何も変わりません。咲こうとする生命力、咲いている力は、人間が生きることと同じです。その生命が美しく、その力がゆたかであるのです。」(P94)。「生き残ったのは、運が良かったのではなく、そこが私の死ぬ場所ではなかっただけのことだと思いました。」(P315)が印象に残りました。
Posted by
- 1
- 2