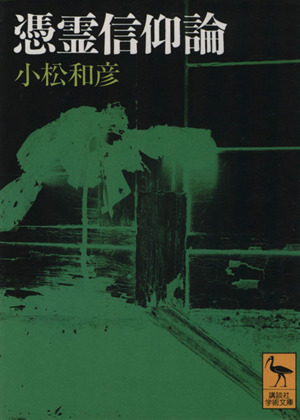憑霊信仰論 の商品レビュー
遠い昔、私が母と祖母が話していた会話を聞いたこと。 「あの人は犬神さんだから」大人になってなんのことやら、と思っていた。 それがこの本で解明されました。 現代の世の中では犬神も何も日本人の万物に対する信仰心さえもうないのですから・・・・ 日本の薄暗い部分、霊や妖怪、祟りなどはも...
遠い昔、私が母と祖母が話していた会話を聞いたこと。 「あの人は犬神さんだから」大人になってなんのことやら、と思っていた。 それがこの本で解明されました。 現代の世の中では犬神も何も日本人の万物に対する信仰心さえもうないのですから・・・・ 日本の薄暗い部分、霊や妖怪、祟りなどはもうありません。 失いたくない部分だったのに。 すべてが白日の下にさらされ、解明されてしまう。 寂しい限りです。
Posted by
メモが残っていないので日時ははっきりしないけれど、椎間板ヘルニアのリハビリに通っている頃に読み切った記憶が。リハビリ先が入院先と違っていた関係で途中バスに乗ってたせいもあって読みは進んだな。 大学在学中に断念してたこの本を、読みきった時は感慨深かった。 目からウロコの内容にも...
メモが残っていないので日時ははっきりしないけれど、椎間板ヘルニアのリハビリに通っている頃に読み切った記憶が。リハビリ先が入院先と違っていた関係で途中バスに乗ってたせいもあって読みは進んだな。 大学在学中に断念してたこの本を、読みきった時は感慨深かった。 目からウロコの内容にもハマッてしまって、すっかり小松和彦先生のファンになってしまった。
Posted by
「憑きもの」信仰について著者がおこなってきた民俗学的調査に基づきつつ、人類学的な観点から考察をおこなっている。 著者はまず、民俗学において「憑きもの」の定義があいまいであることを指摘し、民俗学から解放されたより広い立場から、「つき」の概念の規定をおこなう。たとえばトランプ・ゲー...
「憑きもの」信仰について著者がおこなってきた民俗学的調査に基づきつつ、人類学的な観点から考察をおこなっている。 著者はまず、民俗学において「憑きもの」の定義があいまいであることを指摘し、民俗学から解放されたより広い立場から、「つき」の概念の規定をおこなう。たとえばトランプ・ゲームなどで、特定の誰かが勝ち続けるとき、私たちは「彼はついている」といい、負けの込んでいる他の人々は「こちらはまったくついていない」という。だが、やがて異常な勝ち方がとまると、「彼はつきに見放された」といい、別の人が勝ち始めると、「どうやらつきはこちらにまわってきたらしい」という。 ここで「つき」は、異常な、理解不可能な事態を説明するために用いられている。だが、その「つきもの」がいったい何のことなのか、当人にもまったく不明である。そこでは、「もの」が「つく」という言葉で何かが説明されているように見えるが、じっさいにはその「もの」は何の限定もされていない言葉であり、その実体はまったく理解されていない。 こうした見せかけの説明が生まれる理由を、著者は人類学の「限定された富のイメージ」というモデルを借用して説明を試みる。閉鎖的・自立的村落共同体では、集団の成員間の共同性・協調性が強調され、人々は個人的な地位の上昇よりも集団的な場での名誉を求めることになる。こうした閉じた社会では、一方が何かを多く獲得すれば、他方はその分だけ失っている、というイメージが人々にゆきわたっている。これが「限定された富のイメージ」である。 乏しい富の配分をめぐって、仲間たちとのたえまない闘争によって彩られている社会では、急速に財産をなして上昇する者に対して妬みなどの心理が向けられる。急速に成り上がった者に「憑きもの」というレッテルを貼ることは、そうした社会の平準化のメカニズムとして機能しているのである。 ただし本書の魅力は、こうした人類学的な理論の展開には尽きない。むしろ、いざなぎ流、陰陽師、山姥、器物の妖怪などに関する、著者の幅広い民俗学的研究が、上で紹介したような人類学的な理論的考察を鮮やかに彩っているところに、本書の最大の魅力があるように思う。
Posted by
小松和彦先生の本です。 論文を項目ごとにまとめてます。 「つきもの」の基本的な話から、いざなぎ流陰陽術、山姥、護法信仰についてなど、幅広く展開していきます。 わかりやすくてとても素敵。
Posted by
何かしらの思いを遂げようとして、人の念が憑依し、精霊が人に憑依する。 便利な世の中になったが、今も昔も人の喜怒哀楽はそう変わらないし、「念」というものがどこかで形を変えて残っているのだろうと思う。
Posted by
本書は、一九八二年に伝統と現代社より刊行され、一九八四年には新たに二篇の論文(「熊野の本地-呪詛の構造的意味」「器物の妖怪-付喪神をめぐって」)を加えて、ありな書房から刊行されたものである。
Posted by
憑喪神に興味を抱いたので借りてみたけれど、ボリューミーで濃い内容なのでなかなか読み切れません。とりあえず読みたい章を読んだ感じ。半分くらいか。 (運の)ツキ、憑喪神、座敷童、呪詛、生霊、犬神etc...とにかく「憑依」に関して網羅的に、民族学からではなく人類学の観点から論じら...
憑喪神に興味を抱いたので借りてみたけれど、ボリューミーで濃い内容なのでなかなか読み切れません。とりあえず読みたい章を読んだ感じ。半分くらいか。 (運の)ツキ、憑喪神、座敷童、呪詛、生霊、犬神etc...とにかく「憑依」に関して網羅的に、民族学からではなく人類学の観点から論じられています。変な方向にオカルトオカルトせず、真面目に研究している姿勢がうかがえるので安心して読めます。 クダにつかれた人の行動の異常さも興味深い。・・・あべこべ、さかさまのイメージが垣間見られる。たとえば、「茶碗の手前から食はずに、向こふ側から食ふ」ことや、「痩せていながら家の中をガタガタ」と、まるで大男のように歩く つまりこの神霊は使い方次第で、善にも悪にもなるのである。 言葉も使い方次第で善にも悪にもなるよね。あと式神を使う際には陰陽師本人の文句が必要っていうのも面白いと思う。言葉に出さなければ、具現化しないという意味において。 仏教的にいえば“供養”を、神道的にいえば“祀り上げ”を施さなかったときに、妖怪となって出現することになるのである。 やっぱりモノを大切にとか食べ物を粗末にしないとか、感謝の心を忘れたときに災いが起こる...ものなんだろうか。
Posted by
護法と病気平癒のメカニズムの章がとても面白かったです。護法を召喚して「病人に憑かせる」というのはちょっと盲点だわ・・・
Posted by
小松先生の本を読みだすことになったきっかけ 斬新で面白くかつ分かりやすい 分かりやすい文章を書いてくれる 学者は尊敬する
Posted by
狐憑き、犬神憑き、式神、憑喪神(九十九神)などの憑物、憑依現象、憑物筋について民俗学の視点から詳しく書いてあります。 本というか、まあ論文です。 が、そう難しい文章で書いてあるわけではないので普通に読んで問題ないと思います。京極夏彦氏の京極堂シリーズが好きな方は、一度読んでおいて...
狐憑き、犬神憑き、式神、憑喪神(九十九神)などの憑物、憑依現象、憑物筋について民俗学の視点から詳しく書いてあります。 本というか、まあ論文です。 が、そう難しい文章で書いてあるわけではないので普通に読んで問題ないと思います。京極夏彦氏の京極堂シリーズが好きな方は、一度読んでおいて損はないと思います(笑)
Posted by
- 1
- 2