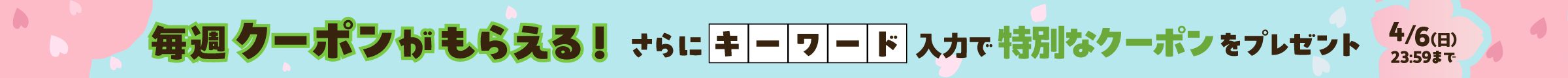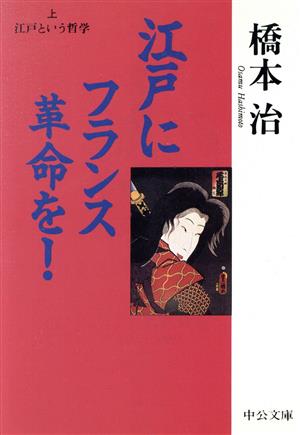江戸にフランス革命を!(上) の商品レビュー
「江戸という哲学」というサブタイトルをもつ上巻は、歌舞伎を中心に江戸の文化についての著者のエッセイがまとめられています。 江戸の現実世界と歴史上のドラマが混然一体になってしまう「リアリズム」を、著者は西洋の幻想文学との対比によって説明しようと試みています。著者の結論は、唯一の神...
「江戸という哲学」というサブタイトルをもつ上巻は、歌舞伎を中心に江戸の文化についての著者のエッセイがまとめられています。 江戸の現実世界と歴史上のドラマが混然一体になってしまう「リアリズム」を、著者は西洋の幻想文学との対比によって説明しようと試みています。著者の結論は、唯一の神が存在している西洋文化では、そうした体制に「対立」が求められるのに対して、日本では現実が平気で非現実へと「逸脱」していくと著者はいい、この「逸脱」を可能にしているのが歌舞伎の「論理」だと論じられます。その「論理」は、「それが論理であると指摘さらた瞬間に雲散霧消してのける」ものであり、そうした歌舞伎の「実相」を享受しているのが江戸の観衆の「リアリズム」であったと著者の議論はつづいていきます。 さらに、こうした江戸の観衆のうちに生きていた「リアリズム」は、近代以降の批評のありようと対比的に論じられています。著者は、学生だったころにある雑誌で江戸時代の役者評判記が引用されていたのを目にして、それに多大な興味をいだきます。それは、近代以降の「批評」のように個人の意見がバラバラに読者の前に提示されているようなものではなかったからです。批評家たちは、そうした批評をおこなうばかりで、そうした自分たちが構成しているはずの「全体」なるものの存在に気づいていないと著者は述べます。そして著者が歌舞伎評判記に見いだしたのは、そのような「全体」への視線でした。 このように、批評の批評性に対する自己言及を、系譜学的なスタイルを通じてさぐっていくところに、いかにも著者らしいと思わされるような知性のパフォーマンスがうかがえるように思います。
Posted by
1994年(著者46歳)に文庫化。上、中、下巻の3分冊(下巻には増補もある)。底本は、1989年(著者41歳)、青土社からの刊本。
Posted by
- 1