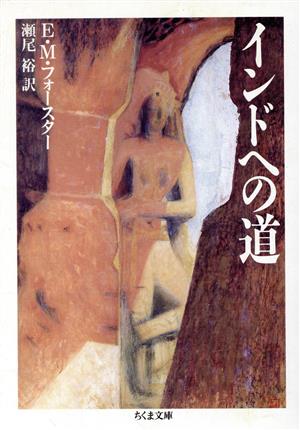インドへの道 の商品レビュー
イギリス支配下のインドを舞台にした、『眺めのいい部屋』や『モーリス』でも有名なフォースターの最後の長編小説。イギリス人統治官とインド人医師の友情と訣別、彼らをめぐる人々の物語を、オリエンタリズムの視点から見るか、同じアジア人の視点から見るかのどちらかで、物語の印象はかなり変わると...
イギリス支配下のインドを舞台にした、『眺めのいい部屋』や『モーリス』でも有名なフォースターの最後の長編小説。イギリス人統治官とインド人医師の友情と訣別、彼らをめぐる人々の物語を、オリエンタリズムの視点から見るか、同じアジア人の視点から見るかのどちらかで、物語の印象はかなり変わると思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
英国支配体制を肯定する立場から、インド社会では異端であった青年医師アジズは、無実の罪で法廷に立たされる。インドに理解の深いことで英国社会で異端であったフィールディングは、アジズを弁護する側にまわる。西洋と東洋とに相互理解はあり得るのか、宗主国と植民地の間に友情は成り立つのか。90年前の小説ながら、古くないテーマ。ただし東洋の神秘性は、90年たった現在、だいぶ割引の必要があろう。
Posted by
ハワーズ・エンドは実務の世界が教養の世界の前に膝を折り傅くのがカタルシスだったが、インドへの道では、さすがに作者の老成を経た価値観が反映されており、やや複雑。読後の素直な感想は、この世に生を受けた異なる価値観が、完全な調和を得られるのは、ふたりの想像の世界においてのみであり、実際...
ハワーズ・エンドは実務の世界が教養の世界の前に膝を折り傅くのがカタルシスだったが、インドへの道では、さすがに作者の老成を経た価値観が反映されており、やや複雑。読後の素直な感想は、この世に生を受けた異なる価値観が、完全な調和を得られるのは、ふたりの想像の世界においてのみであり、実際の世界の制約の中では難しいよでも夢に向かって生きていかなきゃね人間は、ってこと?ふーん。だった。それはそれで激しく同意。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
NHKテレビ3か月トピック英会話 2010 11―聴く読むわかる!英文学の名作名場面 で紹介がありました。 重要表現は I'm afraid I have made a mistake. とのこと。 名場面は Her vision was of several caves. She saw herself in one, and she was also outside it, watching its entrance, for Aziz to pass in. She failed to locate him. It was the doubt that had often visited her, but solid and attractive, like the hills. I am not - Speach was more difficult than vision. I am not quite sure. I beg your pardon? said the Superintendent of Police. I cannot be sure... とのこと。 全体を掴む手がかりになりそうです。
Posted by
これぞ、フォースター!と思わせてくれる一作。読み応えもありますが、何しろインドの描写が細かいので、いきなり読み進めるのに苦労しました。 イギリスの文化やインドの文化がよくわからない、イメージできない方は、ディヴィッド・リーンの遺作でもある映画版を参考に見た方がわかりやすいかもし...
これぞ、フォースター!と思わせてくれる一作。読み応えもありますが、何しろインドの描写が細かいので、いきなり読み進めるのに苦労しました。 イギリスの文化やインドの文化がよくわからない、イメージできない方は、ディヴィッド・リーンの遺作でもある映画版を参考に見た方がわかりやすいかもしれません! 正直、わたしは大英帝国下のインドに関する知識がまったくなかったので、読んでいてへーっ!と思うことばかりでした。 イギリス対インドという構図の中に、在印イギリス対イギリス、回教徒対ヒンドゥー教徒、母対息子、女対男など様々な対立構造が描かれている。 人はあらゆる違いを乗り越えて愛し合うことができるのか。この作品は、フォースターの長編作品におけるその最大の取り組みである。
Posted by
フォースターの作品は4作目くらいか?。 これが一番読みたかったけど翻訳ならびに一言一言に 伏線がある気がしてメモりながら読んだらとっても 時間がかかってしまった。 作品をどうのこうのというよりも、私は作家の方に 興味があって好きで読んでる。 本を読んでるとこの言葉...
フォースターの作品は4作目くらいか?。 これが一番読みたかったけど翻訳ならびに一言一言に 伏線がある気がしてメモりながら読んだらとっても 時間がかかってしまった。 作品をどうのこうのというよりも、私は作家の方に 興味があって好きで読んでる。 本を読んでるとこの言葉がほしかったの!と思うことがある。 人は自分を同調してくれる人や言葉を欲するものだと 思うのだけど、 そのために多くの本に手を出したりする自分もいたりするわけで まさしくこの作品はそれの宝庫なのです。 人間関係の破綻は突然、思いもよらない時と場所で訪れる。 異文化の違いとか、生きた環境・身分の違いとかそういうフェーズの話でも考えられるけど もっと大きな運命論みたいな枠としてもとれる感じ。 この作品に出てくる人物で完璧な人はおらず、どこか 欠陥を持っているし、 常にキャラクターが一貫しておらず、変化して矛盾してたりもする。 でもそれが人間ってもんだし、リアルでいい。
Posted by
- 1