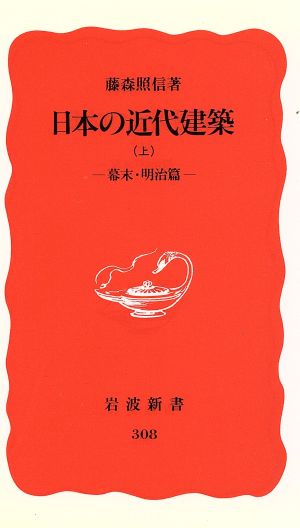日本の近代建築(上 幕末・明治篇) の商品レビュー
幕末から明治にかけて時代が大きく変わっていく中で建築物の存在感が重みを増す。何気なく見ていたレトロな建物には政治が絡み建築様式の対立もありたくさんのストーリーが秘められている。建築を見るには時代背景をよく理解しないといけないね。今まで見た目で判断しかしてなかったから、これからは違...
幕末から明治にかけて時代が大きく変わっていく中で建築物の存在感が重みを増す。何気なく見ていたレトロな建物には政治が絡み建築様式の対立もありたくさんのストーリーが秘められている。建築を見るには時代背景をよく理解しないといけないね。今まで見た目で判断しかしてなかったから、これからは違う視点で見ることができそう。建築の流れを知るには便利な一冊。
Posted by
[ 内容 ] 開国とともに西洋館がやってきた。 地球を東回りにアジアを経て長崎・神戸・横浜へ。 西回りにアメリカを経て北海道へ。 こうして日本の近代建築は始まり、明治政府の近代化政策とともに数多くの作品が造られてゆく。 上巻では、幕末・居留地の西洋館から和洋折衷の洋館、御雇建築家...
[ 内容 ] 開国とともに西洋館がやってきた。 地球を東回りにアジアを経て長崎・神戸・横浜へ。 西回りにアメリカを経て北海道へ。 こうして日本の近代建築は始まり、明治政府の近代化政策とともに数多くの作品が造られてゆく。 上巻では、幕末・居留地の西洋館から和洋折衷の洋館、御雇建築家による本格建築を経て、日本人建築家が誕生するまでを描く。 [ 目次 ] 1 地球を東に回って日本へ―ヴェランダコロニアル建築 2 地球を西に回って日本へ―下見板コロニアルと木骨石造 3 冒険技術者たちの西洋館―洋式工場 4 棟梁たちの西洋館 5 文明開化の華 6 御雇建築家の活躍―歴史主義の導入 7 日本人建築家の誕生―歴史主義の学習 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
今の建築学は西洋建築を教えている。そう言われる理由がわかる本である。 と、同時にこれからの建築も考えさせられる本である。
Posted by
内容(「BOOK」データベースより) 開国とともに西洋館がやってきた。地球を東回りにアジアを経て長崎・神戸・横浜へ。西回りにアメリカを経て北海道へ。こうして日本の近代建築は始まり、明治政府の近代化政策とともに数多くの作品が造られてゆく。上巻では、幕末・居留地の西洋館から...
内容(「BOOK」データベースより) 開国とともに西洋館がやってきた。地球を東回りにアジアを経て長崎・神戸・横浜へ。西回りにアメリカを経て北海道へ。こうして日本の近代建築は始まり、明治政府の近代化政策とともに数多くの作品が造られてゆく。上巻では、幕末・居留地の西洋館から和洋折衷の洋館、御雇建築家による本格建築を経て、日本人建築家が誕生するまでを描く。 目次 1 地球を東に回って日本へ―ヴェランダコロニアル建築 2 地球を西に回って日本へ―下見板コロニアルと木骨石造 3 冒険技術者たちの西洋館―洋式工場 4 棟梁たちの西洋館 5 文明開化の華 6 御雇建築家の活躍―歴史主義の導入 7 日本人建築家の誕生―歴史主義の学習
Posted by
地味だと思っていた日本の近代建築、すごくおもしろかった。 ただひたすら西洋の真似ばっかりしてる時代だと単純に思ってたけど色々あるんですね。よくこれだけ調べたなぁ。 上巻は幕末・明治だけなので、下巻は大正・昭和といったモダニズムの時代になってくるので楽しみ。 日本が開国をしてから...
地味だと思っていた日本の近代建築、すごくおもしろかった。 ただひたすら西洋の真似ばっかりしてる時代だと単純に思ってたけど色々あるんですね。よくこれだけ調べたなぁ。 上巻は幕末・明治だけなので、下巻は大正・昭和といったモダニズムの時代になってくるので楽しみ。 日本が開国をしてから、地球東回りルートからは「ヴェランダコロニアル」が、西回りルートからは「下見板コロニアル」と「木骨石造」が上陸し、ヴェランダと下見板が結合して「下見板ヴェランダコロニアル」が生まれた、という辺りの説明から始まる。 そして、冒険技術者の時代(ウォートルスなど)→偽洋風建築の時代(日本人の技術者)→御雇建築家の時代(アンダーソン・アベレッティ・ボアヴィル→コンドル→エンデ&ベックマン)→そして、日本人建築家の活躍の時代が訪れる。 日本人建築家にはイギリス派(辰野など)、ドイツ派(妻木頼黄など)、フランス派(片山東熊、山口半六)の3つが存在した。第一世代の日本人建築家たちは様式が背負う過去の時代精神や宗教的感情や文化の機敏を理解するのは不可能であったがため、彼らは「用途と様式の関係」と様式が見る人に与える「視覚的印象」の二つを頼りに様式を選ぶしかなかった。この第一世代の建築家の明治期の仕事が、大正と肌分れし、また欧米の同時代と微妙にずれてしまうのは、明治の国家をパトロンとした彼らの作風を染める「国家的な記念碑性の濃さ」であった。 途中、日本人の形式や様式に関するおもしろい考察があった。 P.210 わが国にも様々な建築形式があるが、これらの形式は建物の種類つまり用途に従属している。一方ヨーロッパの様式は建物の種類を越えており、ゴシックは教会だけでなく城にも民家にも採用される。そして、ひとつの作品の中でいくつかのスタイルを並存させることは基本的にはしない。 ヨーロッパの様式の強靭さは時間をも凌ぐ。幾多の再生現象が盛んになりそれにしたがって様々なスタイルが登場する。 こうした様式の再生能力は日本の「○○造り」には欠けており、一度忘れられた様式が何百年か後に復活したためしは例外的にしかない。日本は用途への従属が基本で、古代の神明造りも春日造りも神社が続く限り持続できるが、一方、近世の城郭作りは明治になって用途が終えると消える。ヨーロッパの建築は様式を基礎とし、日本の建築は用途を土台として建つ。 確かにそのとおりかも。こうやって考えると日本の形式の感覚って変わってるなぁと思う。それを考えるとこの時代の日本人建築家の苦労が窺い知れます。
Posted by
幕末後の日本の建築の歴史をたどるために読む。 日本全国の建物に視野が及んでいるので、各地の擬洋風建築が記載されている。松本の開知学校は、実際見たことあるので、リアリティがあった。その後、ジョサイアコンドル始め、工部大学校へと移り変わっていく時代の流れが記載されている。ただ、ジョ...
幕末後の日本の建築の歴史をたどるために読む。 日本全国の建物に視野が及んでいるので、各地の擬洋風建築が記載されている。松本の開知学校は、実際見たことあるので、リアリティがあった。その後、ジョサイアコンドル始め、工部大学校へと移り変わっていく時代の流れが記載されている。ただ、ジョサイア・コンドルの良くなかった点も記述していて欲しかった。
Posted by
近代建築史について。 この著者の文章が好きだということもあるけれど、上下巻とも、建築門外漢の私でも読みやすかった。 割と昔に読んだのでかなり忘れてしまったけれど、赤坂離宮の「ぜいたくだ」の一言は割と印象的だったのでそこだけ覚えている。
Posted by
藤森先生の近代建築史です。非常に読みやすく、上下あわせてさっと読める、初心者にはもってこいだとおもいます。
Posted by
- 1
- 2