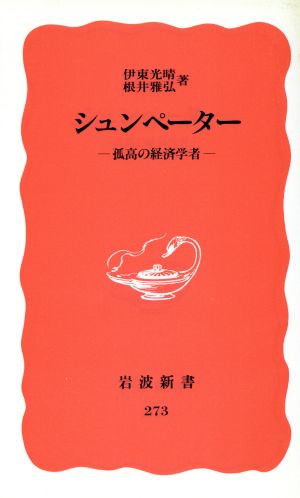シュンペーター の商品レビュー
シュンペーターの人生と思想をまとめた本。 「人生」部分に半分、「思想」部分の半分のページが割り振られている。個人的にシュンペーターの思想の今日的意味を考えるために購入したが、本書はその用途にはお勧めできない。 どうも、タイトルに「シュンペーター-孤高の経済学者-」とあるように...
シュンペーターの人生と思想をまとめた本。 「人生」部分に半分、「思想」部分の半分のページが割り振られている。個人的にシュンペーターの思想の今日的意味を考えるために購入したが、本書はその用途にはお勧めできない。 どうも、タイトルに「シュンペーター-孤高の経済学者-」とあるように、その思想の妥当性や意味よりも、シュンペーターという個人に焦点があたっている。20世紀初頭から終盤にかけて、彼がどのように育ったのか、彼を取り巻く環境はどのようなものだったのか、彼は何を思い、何を感じながら生きたのか、といったことはこれでもかというくらい書いてあるが、21世紀である現在の現象に彼の思想を適用してみる、というような部分は一切ない。 本書はシュンペーターを、「政策と学問は別」とし、現実のゴタゴタした現象とは一定の距離を置き普遍的な事象に集中した人間と解釈しているので、上記のような形になったのかもしれない。いずれにせよ経済史、またはシュンペーターという個人そのものに興味がある人以外には、あまりお勧めできない。 さておき、最後に、シュンペーターの思想をまとめると 「新古典派は均衡状態を現実経済のベースとするが、実際の経済は均衡状態にない。常に均衡状態に向かいつつも、その過程でイノベーションが起こり、不均衡が拡大し、再び均衡状態に向かうというプロセスを断続的に繰り返すものである。イノベーションは、企業家が資源をこれまでとは全く異なる方法で繋げること、すなわち「新結合」によって、実現される。」 となる。 効率的市場仮説やらリアルビジネスサイクルやら、ワルラス以来の均衡理論に基づいた現代経済学がことごとく反駁され、全くとは言わないまでもあまり役に立たないところを見ると、シュンペーターの上記思想は妥当であることが分かる。 ただし、じゃあその「新結合」ってどうやって起こすの?という部分に関して、21世紀の現代、シュンペーターの理論が役に立つことも、またない。彼の思想が、経済学よりも経営学に引き継がれているのは、これが原因だろう。
Posted by
【読書】オーストリアの経済学者であるシュンペーター。以前から勉強したいと思っていた経済学者。本書で指摘するシュンペーター経済学の今日的意味。経済にとって最も重要なものは、技術革新、新製品による新市場の創設、コスト低下による供給曲線のへのシフト。シュンペーターの思想を理解するには、...
【読書】オーストリアの経済学者であるシュンペーター。以前から勉強したいと思っていた経済学者。本書で指摘するシュンペーター経済学の今日的意味。経済にとって最も重要なものは、技術革新、新製品による新市場の創設、コスト低下による供給曲線のへのシフト。シュンペーターの思想を理解するには、彼が生きた時代背景を知ることが有益。しかし、自分なりに彼の思想を理解するにはさらなる経済学の知識が必要であり、もっと勉強が必要。
Posted by
ュンペーターの生涯とその理論をわかりやすく解説しています。前半部分が伝記、後半部分が理論の説明とだいたい2部構成になっています。たしかに、当人の生きた状況や環境を知ったほうが理論も理解しやすくて、この構成はとても良いと思います シュンペーターと聞くと「イノベーション」とか「企業...
ュンペーターの生涯とその理論をわかりやすく解説しています。前半部分が伝記、後半部分が理論の説明とだいたい2部構成になっています。たしかに、当人の生きた状況や環境を知ったほうが理論も理解しやすくて、この構成はとても良いと思います シュンペーターと聞くと「イノベーション」とか「企業家」とかという言葉がすぐ思い出されて、経営学より実務よりの経済学者なのかなあ、と勝手に想像していました。でも、前半部分を読むとあまり実務的ににおいがしない。典型的な学者といった印象で、あれれ、とちょっと戸惑ってしまいました。それも、後半部分の理論を読んではっきりしました。 シュンペーターの感心はあくまでも、経済学の本流の均衡理論の動態的研究なんですね。需要と供給が均衡して利潤ゼロ、はい、おわり。という静態的状態から、どうやって経済が発展していくのか、ということの原理を模索していた。そこで供給曲線が非連続的にシフトする原動力がイノベーションであって、イノベーションの担い手こそが企業家だということのようです。そうしたイノベーションによる供給曲線のシフトが景気循環をも生み出すことになる。なるほど、イノベーション・企業家と景気循環とがイメージの中ではつながらなかったのだけど、実は非常にシンプルでかつ密接な関係だったのか。 途中、マルクス経済学との関係のあたりはあまりよくわからなかったのですが、イノベーション、企業家、景気循環とった主要な言葉の意味するところは、なんとなくわかったかなーと。いや、わかったとはいわないまでも、いままでのおかしなイメージが払拭されただけでも大収穫でした。
Posted by
著しく遅読な私であるが、この本は二日で読みきることができた。 先ずなにより、シュンペーターは、ケインズのような「政策論」を著しく嫌ったようである。それは彼の著書の中にも現れている。彼は「政策」と「学問」は別であると、いつも豪語していた。 彼はワルラスを敬愛していたとよく伝え...
著しく遅読な私であるが、この本は二日で読みきることができた。 先ずなにより、シュンペーターは、ケインズのような「政策論」を著しく嫌ったようである。それは彼の著書の中にも現れている。彼は「政策」と「学問」は別であると、いつも豪語していた。 彼はワルラスを敬愛していたとよく伝えられるが、敬愛すると同時に、失望もしていた。彼の均衡理論は極めて「静学的」であったため、シュンペーターは経済学において常に「動学」を重要視していたことからも、ワルラスの均衡理論はその殻をぶち壊すものであった。彼は起業家の「新結合」が資本主義を発展させると考えていた。 また彼はホブソンやレーニン、ヒルファディングと同様、帝国主義にも言及をしていた。シュンペーターはドイツの「前近代性」や「後進性」に焦点を当て「健全な資本主義の元では帝国主義は起こりにくい」と考えており、それがレーニンやヒルファディングの考えるものとは違う、と考えた。 しかしながら、宇野理論は正しくこの通りなのである。帝国主義段階は、「自己を純粋化させる方向ではない。」としているし、シュンペーターは「本来ならば、自由経済を志向する者たちは、帝国主義的政策を希望しない。」としている。勿論関税その他の規制は、直接的に恩恵を受ける企業しかうるおわない。これは宇野理論でも、「市場とは別に価格が設定されるから、利潤は極大化される。」としている。これはシュンペーターの予言通りではなかろうか。 シュンペーターは常に「冷静な観察者」足りえた。彼の理論はマルクスのそれと似通っているところが少なくないが、マルクスも資本主義を仔細に研究した。そこに同根性を見出すのに、興味がわくところである。
Posted by
ケインズと同時代に生きたものの、そのスタンスは好対照。 政治経済学の復活をもたらし、自らの理論を片手に現実を切り開いたケインズに対し、あくまで経済理論の包括的完成を試みたオーストリア学派の経済学者、シュンペーター。 新書としては理想的な内容。
Posted by
景気循環にはイノベーションが必要というそれまで経済学にはなかった独自の理論を展開するシュンペーターについて書いた一冊。
Posted by
- 1
- 2