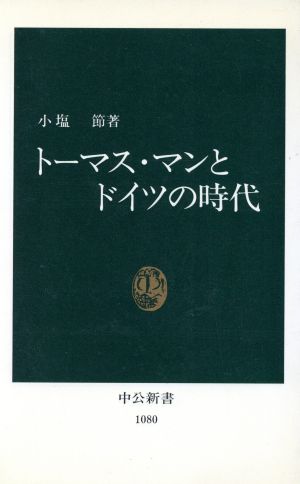トーマス・マンとドイツの時代 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読んでみた人であればわかると思いますが、トーマス・マンの著作はなかなか難解です。彼の作品に込めた思いやその背景を理解したく、本書を手に取りました。 この手の解説本がよくとる説明手法として、著者の生涯とその中で生まれた作品とを照らし合わせて解説する、といったものでしょう。結局この手法がもっとも効率的に著者と著作の解説ができるからでしょうが、本書もそのような形式で解説がなされています。 トーマス・マンは1875年に北ドイツの港町リューベックで生まれ、19歳となった1894年の春にミュンヘンに移住。ナチスから逃れて亡命の旅に出るまでの40年間をここで過ごします。 リューベックは商業の街であり、プロテスタントの宗教性を背景とした勤勉さの息づいています。代表作である『ブッデンブローク家の人びと』やその他の作品にもその描写や影響がみられることが説明されています。 マンが16歳のころ父親が51歳でこの世を去り、これを機に100年以上続いた「マン穀物商会」が解散します。息子たちは誰もあとを継がなかったからですが、『ブッデンブローク家の人びと』にもこれの経緯を思わせるような描写がいかように説明されており、興味深い。 「堅実な市民の家系が、代を重ねていくうちに次第にたくましい生命力を失っていき、それにつれて逆に文化的センスは洗練されていき、一種の精神的なデカダンスにおちていきながら、高い梢の上に芸術的な美しい花を咲かせる。」 これはマンのある種の弁明なのかもしれない。 名作『トニオ・クレーガー』のこの延長線でかたられます。ここで解説される物語の構図や心理的背景については審美的でありセンチメンタルであり、心が惹かれます。 「最も多く愛する者は敗者であり、悩まねばならぬ」 後年になり、マン自身が「私の書いたすべてのものの中で、今日でも私の心に最も近い」作品だと述べており、本書からマンの感性をうかがい知ることができるでしょう。 時はナチスが支配する暗黒の時代に入り、マンは悩んだ末、亡命を決意します。 マン自身はだいぶ優柔不断な上にカンの鈍い性格だったらしく(これは意外でした)、亡命に際しては長女のエーリカが大活躍します。ちなみにエーリカはかなりの女傑であったらしく、ナチス監視下の自宅から執筆中であった『ヨセフとその兄弟』の原稿を持ち出したり(彼女がいなければこの大作が世に出ることはなかったことになります)、またナチスの監視を見越してマンにドイツ帰国を思いとどまらせたのも彼女でした(この時マンに伝えた暗黙のメッセージ「こちらは天気が悪い」のくだりは小説のようで面白い)。そのほかの子供たちも個性派ぞろいで、本書でも詳しく取り上げられています。 本書の終盤では一章(Ⅳドイツ人、トーマス・マン)を割いて、マンのドイツに対する認識・評価を取り上げています。 ドイツは二度の大戦を引き起こし、世界の厄介者として扱われることになった。一方で音楽をはじめとする文化的な影響を世界に及ぼしてきた。国土はたびたび荒廃し、そのたびに復活してきた。このようなドイツをどうとらえればよいか、というのが主要なテーマだと感じました。 「悪しきドイツ、それは道を誤った良きドイツであり、不幸と罪と破滅の中にある良きドイツである。」 これはとても深い描写だと思います。 息子のゴーロによると、亡命中にあっても彼の家ではドイツ語以外の言葉を用いてはならなかった。また書斎の壁には「私のいるところに、ドイツがある」という自筆の言葉が貼られていた。マンはいかなる境遇にあってもドイツを愛しており、そのために苦悩したことがこの一章を通して語られています。 一方で本書ではマンの日常や習慣に触れた記述もふんだんにあり、その内容に気が和みます。 「たとえば、毎日、朝のコーヒーの後は身づくろいを正し、正確に9時から13時まで仕事部屋に入って、一心不乱に執筆をした。休暇中も亡命中も、修正これを怠らなかった。」 「すでにタイプライターは発達していた。 ・・・ それなのに、トーマス・マンは若い時から後年大作家とされ多忙を極めた年月にも、原稿と手紙はすべて一字一字心を込めて手で書いた。」 「朝食のコーヒーは必ず一杯半。三分間ゆでた卵を一個半と決めていた。二個は取らなかった。残りの半分はどうしたのだろう?」 また妻であるカチア・マンを取り上げた一節は個人的に必読です。 ここには著者の恋慕にも似た心情が暗に表現されており、まるで小説のような描写に少し心が奪われました。
Posted by
- 1