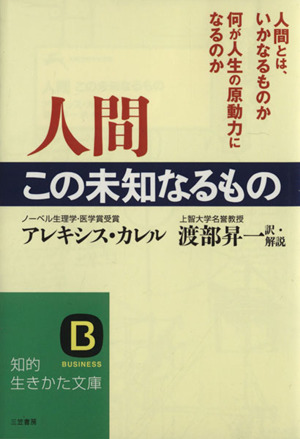人間 この未知なるもの の商品レビュー
ノーベル生理学医学…
ノーベル生理学医学賞受賞の著者が、人間とは何か、肉体と精神の両面を考察。全世界で一千万部突破の書。賛同できない記述もあり、1935年の発表であるということを考慮する必要はある。
文庫OFF
人間については 誰…
人間については 誰もが良く分かっているようでもあり まだまだ多くの謎に包まれている。自分のことすら分からないことがたくさんあって そういう意味では人生短すぎるのかもしれない
文庫OFF
なんと素晴らしい本でしょう。人間が生体学的にどのような構造で作られ、それと精神的な心とはどのように関連しあい、どのような方向に向かおうとしているのか、また未だに人間についてはよく分かっていない、私たちはまだまだ膨大に未知なる存在であることがこの本を通してよくわかります。 実に何も...
なんと素晴らしい本でしょう。人間が生体学的にどのような構造で作られ、それと精神的な心とはどのように関連しあい、どのような方向に向かおうとしているのか、また未だに人間についてはよく分かっていない、私たちはまだまだ膨大に未知なる存在であることがこの本を通してよくわかります。 実に何もわかっていない自分が世の中のことや人のことが大体はわかっていると、勝手に誤解し、認識して生きていること自体が既に迷いながら生きていると言うことに気付かされます。 この本は人間と言うものが一体どんな存在であり、どうしたら成長できるのか、どういう環境が人間を退化へと導くのか、物理的化学的また精神的にまたそれ以上に、複雑な部分から人間ができていることを詳細に克明に解説している本であり、これほど人間を成長させ向上させ、また逞しくさせる礎となる本は無いかもしれません。 ぜひ一度を進めたい本と言えます。
Posted by
今から84年前の1935年に初めて出版、 ノーベル生理学・医学賞受賞しているアレキシス・カレルが著した『人間この未知なるもの』 医学者の立場から人間という存在に切り込む。 教養深い人物でただの専門家ではない洞察がうかがえる。 そして、非常にリアリストな側面を持つ。 「人...
今から84年前の1935年に初めて出版、 ノーベル生理学・医学賞受賞しているアレキシス・カレルが著した『人間この未知なるもの』 医学者の立場から人間という存在に切り込む。 教養深い人物でただの専門家ではない洞察がうかがえる。 そして、非常にリアリストな側面を持つ。 「人間」は平等であるが「個人」はそうではない。 「個人」には相違があり、それは尊重されるべきものであり、弱者と強弱を画一的に規定する社会状況が強者の発展、強いては社会発展の弊害となると説く。 白人至上主義の気があるが、これは本質的には優位性を尊重すべきという観念からきているのだろう。 医学の進歩により、 従来であれば虚弱体質で死んでいた人間も生きれるようになった。 また、肉体的・精神的・知的に鍛錬がなされていない、もしくは遺伝的に劣った人間ほど子供をつくり、優位性のある人ほど子供をつくらないということを憂いている。そうした一連の流れが民族を弱体化させると。 ここは福沢諭吉の「学問のすすめ」にも相通ずるところがある。 勉強してない夫婦の子供は益々勉強しないことによって社会にとって益をなさないと。 各人にとって適性のあることを各人のレベルでできることをやる。 先天的、後天的というのはあるが与えられたカードで人生を生きていく。 そして、優れたものがより優れた成長を得て、結果弱者も恩恵を受ける。 各個人の才能を適材適所で活かせる社会を築いていき、各人が修練を続けていくことが大事。 全世界1000万部のベストセラー。
Posted by
アレクシス・カレル(1873~1944年)はフランスの外科医、解剖学者。1912年に血管縫合および血管と臓器の移植に関する研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した。 本作品は、第二次世界大戦の始まる4年前の1935年に書かれ、発売直後から世界各国で翻訳されて、発行部数はこれまで全世...
アレクシス・カレル(1873~1944年)はフランスの外科医、解剖学者。1912年に血管縫合および血管と臓器の移植に関する研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した。 本作品は、第二次世界大戦の始まる4年前の1935年に書かれ、発売直後から世界各国で翻訳されて、発行部数はこれまで全世界で一千万部を超えると言われるベストセラーである。日本でも1938年に初めての訳本が出版され、その後も様々な出版社から繰り返し再刊されているが、最近新刊で手に入るのは故・渡部昇一訳の本書である。 本書は、「ノーベル賞学者が、医学的知見に基づいて、人間とは何か、人生とは何か、を考察した人生哲学の啓蒙書」との評価により(渡部昇一も「最高の恩書」と記している)ベストセラーとなったが、下記の通り、(時代背景もあるのかも知れないが)大きな問題を含んだものである。 全体を通した要旨は以下であり、発表後80年を経ても古さを感じさせず、寧ろその危機感と対応の必要性は高まっているとさえ言える。 ◆われわれ現代人は、無生物に対する科学の進歩により現代文明を作り上げてきたが、人間を知ること(「人間の科学」)を疎かにしてきたために自然な生存の状態を脅かされるようになった。 ◆「人間の科学」に必要なことは、人間を部分に分けて分析することではなく、人間に関わる全て(構造と環境に対する肉体的、化学的、精神的な諸関係)を、総合的に研究することである。人間の「生理的」な活動と「精神的」な活動は相反したものではなく、一個の複合体として研究しなくてはいけない。 ◆われわれは、盲目的な科学技術から人間を解放し、複雑かつ極めて豊かな人間本来の性質を把握しなければならない。そうすれば、人間は、過去の偉大な文明すべてに共通した崩壊という運命から逃れることができる。 ところが、その手段のひとつとして著者が主張するのは、ナチスが唱えた「優生学」である。「各人の権利は平等である、というのは幻想である。精神薄弱児と天才が、法の前に平等であるべきではない」、「平等の理念は、エリートの成長を阻害することで文明の崩壊に力を貸してきている」、「優生学は、強い者を永続させるために絶対必要である。優秀な民族は、その最善の要素を増殖しなければならない。だが、最も高度に文明化した諸国家においては、再生産は減少し、質の劣ったものが生まれてきているのだ」という、驚くような記述が続いている。白人優位的な表現も目に付く。 「人間重視」、「部分ではなく全体で」という主張には賛同するが、(当時の時代背景はあったにせよ)通底する「人種差別」、「弱者差別」の思想は到底容認するわけにはいかない。 本書を読むにあたっては、著者の主張の善悪を自ら判断する力が不可欠である。 (2018年11月)
Posted by
ノーベル生理学賞受賞者である著者による、古典的医学、生物学、および、彼の政治的思想の解説書である。医学、生物学の解説は、70年のときを経ているため信じるに足りないことも多く、特に読む必要はないと思われる。 本書での特筆すべき点は、後者である政治的思想である。淘汰を受けない人類(彼...
ノーベル生理学賞受賞者である著者による、古典的医学、生物学、および、彼の政治的思想の解説書である。医学、生物学の解説は、70年のときを経ているため信じるに足りないことも多く、特に読む必要はないと思われる。 本書での特筆すべき点は、後者である政治的思想である。淘汰を受けない人類(彼は、西洋人についてのみ語っている。当時の人種差別当たり前の時世ではしかたないだろう)の劣化、退化を非常に危惧している。また、女性の社会進出による少子化や生育の劣化を予言し、「女権拡張運動の推進者たちは、男女両性が同じ教育、同じ権利、同じ責任を持つべきであると信じるようになった。・・・女性は男性を真似ようとせず、その本質に従って、その適正を発展させるべきである。文明の進歩の中で、女性の担う役割は男性のものよりも大きい。女性は、自分独自の機能を放棄してはならないのである」と。まさに、わが意を得たりと感じる(というと、田島陽子的御バカさんが女性蔑視だというだろうが、これは蔑視でも差別でもない)。 この本に対しては、人種差別による選民思想を科学的に裏付けているというような批判もあるようだが、思想の時代的背景を考えると、そのような批判は当たらないと思う。むしろ、現代社会の行き過ぎだ平等主義、人権主義に対する警鐘と受け止めるべきであろう。
Posted by
豊かになって、それまでは自然への適応が科学の中心だったが、人間自身に目が向くようになった。 断食は飢餓状態をつくるという効果がある。
Posted by
ノーベル生理学・医学賞受賞者である著者が、人間の本性と未来を考察した本。 理系・文系の壁を超えた叡智の集積といった感じ。 丹羽宇一郎氏推薦の本だけあって、とても濃い内容だ。 丹羽氏は『リーダーのための仕事論』のなかで、リーダーが持つべき教養や人間力を強調しているが、人間を深く理解...
ノーベル生理学・医学賞受賞者である著者が、人間の本性と未来を考察した本。 理系・文系の壁を超えた叡智の集積といった感じ。 丹羽宇一郎氏推薦の本だけあって、とても濃い内容だ。 丹羽氏は『リーダーのための仕事論』のなかで、リーダーが持つべき教養や人間力を強調しているが、人間を深く理解するための書として本書をすすめる理由がよくわかる。と同時に、彼の求める教養のレベルがよくわかる一冊だ。 1935年の本なので、時代錯誤な部分もあるが、逆にその時代から今を見通している部分が多いことに惹きつけられる。
Posted by
内容があまりに厳しすぎて、正論であるが故に残酷。 現代社会を生きるの人間への、過剰とも思えるほどの危機感が感じられる。 人間って生き物を客観的に分析し、現代の社会における人間のあり方と、向かうべき方向を具体的かつ容赦なく示してる。 まるで近現代の日本を俯瞰して、日本の未来に警...
内容があまりに厳しすぎて、正論であるが故に残酷。 現代社会を生きるの人間への、過剰とも思えるほどの危機感が感じられる。 人間って生き物を客観的に分析し、現代の社会における人間のあり方と、向かうべき方向を具体的かつ容赦なく示してる。 まるで近現代の日本を俯瞰して、日本の未来に警笛を鳴らしているかのように感じる部分が多々ある。 ただ、筆者の述べるところに沿って社会を再構成すると、社会は厳密すぎて硬直してしまい、一切「遊び(余裕)」の無い状態に陥りはしないか。 想像だにしない事態へのリスクヘッジとしての「混沌」を、あえて残すべきじゃないかとも思う。 適度な余裕と、一見無駄とも思える「ゆらぎ」のなかから新しい価値は生まれ出ると思う。 だから僕は、筆者の求める世界に危うさを感じる。 6章『人間自身を「ふるい」にかけなければならない』より抜粋 われわれは、文明化している一般大衆の中から選択をしなければならない。長期間にわたって自然淘汰が行われていないことは、すでに述べたとおりである。衛生学と医学の努力により、かくも多くの劣弱者が生き延びていることもすでに述べたとおりである。しかし、狂人か犯罪者でない限り、劣弱者がまた劣弱者を生み出すのを防ぐ事はできない。また、同じ母親から一緒に生まれた子犬のうち弱い物は殺すように、病気や不具の子供を殺すわけにはいかない。劣弱者がはびこる破滅的な危険を未然に防ぐ方法はただ一つ、強者を一層発達させることである。不適格者を正常にしようと努力しても、無駄なことは明らかである。・・・ こんな具合だから、当然今の日本のテレビじゃ紹介されないだろうし、公のメディアからの情報だけでは触れることの出来ない考えだと思う。 だから”本”ってすきやねん。
Posted by
- 1