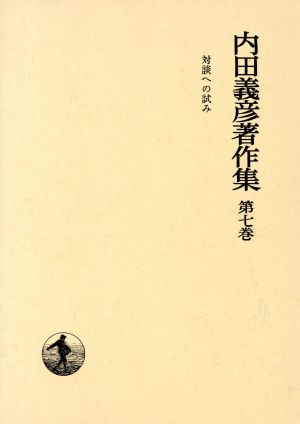内田義彦著作集(第7巻) の商品レビュー
2021/8/10 内田義彦の音楽との向き合い方はとても参考になる。スコア買って体全身を使って指揮してみようw また、教育に関する対談では、大学のあり方というのを再考させられた。高度経済成長以後、大学生のあり様さほど変わっておらず、現代にも十分通じる話だ。 ビジョンなきニヒ...
2021/8/10 内田義彦の音楽との向き合い方はとても参考になる。スコア買って体全身を使って指揮してみようw また、教育に関する対談では、大学のあり方というのを再考させられた。高度経済成長以後、大学生のあり様さほど変わっておらず、現代にも十分通じる話だ。 ビジョンなきニヒリズムにどう立ち向かうかというのは人生の大問題であるが、それは「学問的な探究的な精神」が打破すると喝破する。 これを読んで、大学で学び直すことの意義を改めて考えさせられた。関連して、ゲーテが学びについて書いている一節が先日から何故か頭にこびりついて離れないので、ここに書き留めておく。 「ぼくはちょうど塔を建てようとして、卑劣な基礎工事をしてしまった建築師のようなものである。彼は早くそのことに気づき、すでに地中から築きあげたものをいさぎよく破壊し、基礎を拡大し改良し、土台をもっと堅固なものになることをすでにいまから楽しんでいるのである。」 ーーーメモーーー レコードでは分からないが、音楽は地域の伝統によって形作られている。カラヤンとベルリンフィルの独自性。 → 音楽をレコード化するとデータが省略される(川添愛) 音楽にはー音楽が抽象的であるだけにーいろんな他のジャンルで得た、あるいは得られる体験が抽象化されて入りこんでいて、そういう形で複雑で具体的な現実と連なっているような気がするんだな。抽象的であるがゆえにその全体に浸透し、全体を統合するものとしての音楽がある。 モラトリアムという本来の意味というか、() 教育学的含意は、自分の人生選択にじっくり時間をかけて、自分の可能性を発見し、自分を実現していく、その人生選択と自己実現のための準備期間。 ですからその意味で、そのモラトリアムの期間というのはまさに自分を突きつめながら、自分の個性を発見し、アイデンティティを確立する、そきて自分の個性を社会でどう生かすかというしかたで社会のあり方を批判的に見通すような () それは学問的な探究的な精神をみずからのものにすることによって可能になる。
Posted by
- 1