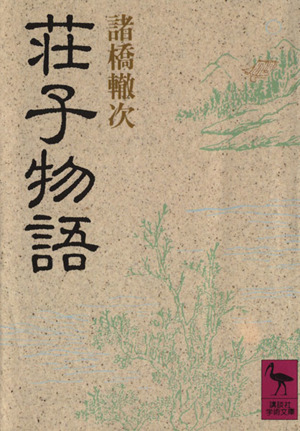荘子物語 の商品レビュー
荘子全編をテーマごと…
荘子全編をテーマごとに再編集して物語形式にしています。著者の荘子観が良く現れており、荘子入門にも好適だと思います。この本の読了後は、中公クラシックで出ている全訳を読むことをお勧めします。
文庫OFF
生きづらい現代には老荘思想が良いと聞いて、初めて荘子に関する本を読んだ。 面白いと感じたし、もっと詳しく老荘思想について知りたいとも思えた。 まだ理解できていないのか、深く読む必要がないのか判断できないけれど、荘子は議論や勉強は必要ないといっているのにも関わらず、荘子自身は議論や...
生きづらい現代には老荘思想が良いと聞いて、初めて荘子に関する本を読んだ。 面白いと感じたし、もっと詳しく老荘思想について知りたいとも思えた。 まだ理解できていないのか、深く読む必要がないのか判断できないけれど、荘子は議論や勉強は必要ないといっているのにも関わらず、荘子自身は議論や勉強を好んでいるように感じた。 また死については、自然にというが、長生きも推奨されているように感じた。 結果、自分にはよく分からないが、面白い話も、なるほどと思うような話もたくさんあって夢中になれた。
Posted by
自説のためとはいえ孔子をこき下ろす荘子のことも明快に解説。 諸橋先生の知識が広範なので他の諸氏百家のこともかじれる仕様。 それより特筆すべきは後ろの帯文。編者か売り手か分からんが相当な諸橋先生ファンなのかクールにかつ熱く推薦してくれてつい読みたくなります。
Posted by
荘子という人にやや焦点をしぼっている。 なべて老荘の思想は空漠としていて、実践的でない。かつ論理的でない、ともすれば詭弁的な神秘思想である。 原始仏教に通ずる考え方もある。しかし、実践的かつ理論的という意味で仏教思想のほうがすぐれていると感じる。
Posted by
「大漢和辞典」編者の諸橋轍次先生による荘子を巡る物語。いわゆる荘子著とされる一連の書についての一般向け解説書であるが、「はしがき」に曰く「外篇・雑篇には勿論後人の筆も多かろうが、いずれは荘子にあやかっている一群の人々だ。時代も既に遠い昔の事だから、これら一群の人々をも、今は併せ...
「大漢和辞典」編者の諸橋轍次先生による荘子を巡る物語。いわゆる荘子著とされる一連の書についての一般向け解説書であるが、「はしがき」に曰く「外篇・雑篇には勿論後人の筆も多かろうが、いずれは荘子にあやかっている一群の人々だ。時代も既に遠い昔の事だから、これら一群の人々をも、今は併せて一人の荘子としてこの物語を纏めた。」とある。 荘子の思想を解説するに当たって、老子の思想をも紹介しており、単に荘子に関する書にとどまらない。興味深いのは決して荘子礼賛ではなく、適宜諸橋先生による批評が入っているところである。荘子について、「多弁家であり、能弁家でありますから、時には心にもないことをまで、口から走り出るままにしゃべるのであります。」(P248)「ここまで極端な議論になりますと、荘子も一介の詭弁家になり下がった感があります。」(P249)と評する。これには賛否あるかもしれないが、漢籍に詳しくないものが「昔の偉い人」の言う事に盲従しないためにもなかなかに良い取り組みではないかと思うのである。 また、荘子が「昔の偉い人」である孔子の思想をも利用していることを看破し、「この辺の文章は例の巧みな荘子の詭弁で、漸次孔子の教えを自分流に降参させようとしているのであります。なかなか油断はなりません。」(P147)と警告を鳴らす。漢籍を縦横に読みつくした先生ならではの謂にうならざるを得ない。 滔々たる大海である漢籍の世界を、隅々まで知り尽くした老師の背に乗って遊び歩くような書である。漢籍を読んでみたいがどこから手をつけて良いかわからない、という人に進めてみたい一冊だ。
Posted by
老荘思想を講話風のわかりやすい文章で解説した一冊。寓話が達者で極論を好む荘子は、思想的にその多くを老子に負っていることもあって、単なる詭弁家とも思われがちだが、それでも彼の文章の巧みさは今なお人々の惹きつけてやまない。彼の主張は極論や矛盾だと切って捨てるのは容易だが、そのような荘...
老荘思想を講話風のわかりやすい文章で解説した一冊。寓話が達者で極論を好む荘子は、思想的にその多くを老子に負っていることもあって、単なる詭弁家とも思われがちだが、それでも彼の文章の巧みさは今なお人々の惹きつけてやまない。彼の主張は極論や矛盾だと切って捨てるのは容易だが、そのような荘子独特の物言いによって何を言わんとしているのか解釈を試みるのは楽しく、そのためには良質の手引きが必要だ。読みやすく書かれているが、入門書としてさらっと読み流すよりもじっくり味わって読みたい一冊。
Posted by
- 1